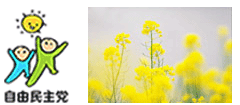議会レポート
平成12年12月
|
|

|
温室効果ガスの削減に向け
環境県千葉としての努力を
|
■循環型社会■ 岡村 平成12年6月に制定された循環型社会形成推進基本法とあわせて、いわゆるグリーン購入法が制定され、国においては、この法律に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針案が発表された。 東城環境生活部長 県では、平成9年3月に「ちば新時代エコ・オフィスプラン」を策定し、日常業務における環境配慮事項として、エネルギー利用の抑制や再生紙の利用等7分野にわたって取組事項を設定し、率先して環境保全に配慮した取り組みを進めている。 岡村 県では、グリーン調達の対象物品として、どのようなものを考えているのか。 東城環境生活部長 グリーン購入法では、国において、自らの環境物品等の調達の推進に関する基本方針を定めることとされており、この基本方針では、重点的に調達すべき物品等の種類とその判断基準及びこの判断基準を満たす物品等の調達に関する目標のたて方が盛り込まれることとなっている。 岡村 容器包装リサイクル法が平成9年にスタートし、平成12年4月から対象品目として紙製、プラスチック製の容器包装が追加されたほか、再商品化義務を負う事業者の範囲に中小企業者が加えられた。 東城環境生活部長 平成9年度に、容器包装廃棄物の減量及び再商品化を目的とする容器包装リサイクル法が施行されて以来、地域住民の協力と市町村の努力のもと鋭意その推進が図られており、平成11年度における本県の分別収集量は約9万5000トンで全国第3位となっている。 岡村 家電リサイクル法が、平成13年4月から本格的に施行されるが、この制度の効果についてどう考えているのか。 東城環境生活部長 家電リサイクル法は、従来、その大部分が埋立処分されてきた使用済家電製品について、消費者に費用負担を求め、製造業者がリサイクルの義務を負うという新しいシステムにより、廃棄物の適正処理と資源の有効利用を目指すものである。 岡村 家電リサイクル法を円滑に運用するため、住民にわかりやすく周知すべきと思うがどうか。 東城環境生活部長 家電リサイクル法においては、消費者は排出家電製品を適正に小売業者に引き渡し、収集・運搬及び再商品化に要する費用を負担するということとされており、この制度を幅広く周知させることは、同法の円滑な施行を図る上で極めて重要と考えている。 岡村 建設リサイクル法が成立し、平成12年5月31日に公布されたが、同法の施行に向けて、県はどのように取り組もうとしているのか。 武藤土木部長 本県では、公共事業から生じる建設廃棄物や建設発生土の発生の抑制、再利用の促進等を図るため、千葉県建設リサイクル推進計画を策定し、各種施策に取り組んでいる。 岡村 四街道市にある最終処分場の現状及び今後の指導については、どのように考えているのか。 東城環境生活部長 昭和61年11月に設置届が出された四街道市の最終処分場の埋立容量は、約14万立方メートルで、平成12年9月末現在での残存容量は、約2万立方メートルとなっている。 |
|
■地球温暖化防止■ 岡村 県は、温室効果ガスの削減を図るため、森林の吸収量を見込んでいない「千葉県地球温暖化防止計画(案)」を、平成12年11月9日に千葉県環境審議会に諮問したと聞いている。 東城環境生活部長 千葉県地球温暖化防止計画(案)に掲げる削減目標は、 岡村 計画の推進には、県民の理解と協力が重要と考えるが、県民に対してどのように普及啓発を進めていくのか。 東城環境生活部長 地球温暖化問題にかかわらず、県民一人ひとりが環境保全意識の向上を図ることが大変重要な課題であり、幼いころから自らの問題として環境を考え行動する知識や知恵を身につけることが大切であると認識している。 岡村 計画における県自らの温室効果ガスの削減をどのように進めていくのか。 東城環境生活部長 県では、平成9年3月に「ちば新時代エコ・オフィスプラン」を策定して、日常業務における環境配慮事項として、電力やガス等のエネルギー利用に伴い排出される二酸化炭素を抑制する取り組みを行ってきた。 |
|
■ダイオキシン■ 岡村 ダイオキシン類対策特別措置法は、平成12年1月15日に施行され、廃棄物焼却炉等の特定施設とこれらの施設が遵守すべき排出基準を定めるとともに、知事は立入検査を行うことができるとされている。 東城環境生活部長 ダイオキシン類対策特別措置法が平成12年1月15日から施行されたことに伴い、平成12年度から同法に基づく大気基準適用施設を設置する事業場に対して立入検査を行っており、9月末現在、121事業場、160施設の立入検査を実施した。 岡村 平成13年1月から排出基準が適用される施設に対して、県はどのように検査を実施していくのか。 東城環境生活部長 ダイオキシン類対策特別措置法施行日以前に設置され、平成13年1月から排出基準が適用される既設の施設に対しては、すべての施設について立入検査を実施する方針であるが、当面は、 |
|
■ディーゼル車対策■ 岡村 平成12年11月7日にかずさアークで開催した七都県市首脳会議の場では、知事が座長としてディーゼル車対策をまとめ、七都県市として共同した取り組みを行っていくことが合意されたとの報道があった。 沼田知事 7都県市では、自動車排出ガス対策は広域的な取り組みが必要であることから、従前から冬期自動車排出ガス対策の「ぐるっと青空キャンペーン」の共同実施や七都県市指定低公害車の指定及びその普及等に取り組んできた。 岡村 今後、7都県市で共同して取り組むとしているが、県はどう対応するのか。 沼田知事 平成12年11月7日に、かずさアークで開催した7都県市首脳会議において、現在走行している使用過程のディーゼル車の対策が極めて重要であることを合意し、天然ガス自動車に代表される窒素酸化物や粒子状物質の排出量の少ない低公害な自動車の普及を共同・協調して推進していくことを、座長として取りまとめた。 |
|
■大気汚染■ 岡村 平成11年度の大気環境調査結果によると、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについては、全地点で環境基準を達成しているが、ベンゼンについては、18の測定地点のうち、都市部や京葉臨海部を中心に11地点で環境基準を超過している状況にある。 東城環境生活部長 ベンゼンは、合成ゴム、合成樹脂等の化学製品の原料や溶剤として使用されていることから、大気汚染防止法において、ベンゼンの指定物質排出施設として貯蔵タンク等6種類を定めており、県内では、石油化学工場等、10の事業所において61施設が設置されている。 岡村 排出量の抑制に向け、どのように対応していくのか。 東城環境生活部長 ガソリン燃料中のベンゼンの低減については、国において、自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を改正し、平成12年1月1日からベンゼンの許容限度が従来の5%から1%と、五分の一に強化されている。 |