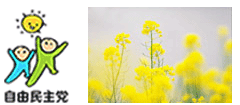議会レポート
平成12年6月
|
|

|
ダイオキシン類の環境調査の実施と
有効な排出抑制対策を
|
■地区社会福祉協議会■ 岡村 県は、社会福祉基礎構造改革の中でも、個人の自立を基本とし、地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実を理念の三本柱の一つに掲げ、ゴールドプラン21の四本柱の一つにも支え合う地域福祉の形成を掲げ、住民同士による支え合いのネットワークづくり、地域活動の拠点づくりを積極的に展開しようとしている。 沼田知事 地区福祉の推進に当たっては、県民の相互連帯に根差した自発的福祉活動が重要な役割を果たすものである。 |
|
■福祉行政■ 岡村 施設入所者は、夕食時間が早過ぎたり、おむつ交換等プライバシーをもっと考えたケアをしてもらいたい等の施設の福祉サービスに対する様々な要望、苦情を抱えており、また、虐待等人権にかかわるものもある。 沼田知事 社会福祉法の施行により、施設入所者の保護を目的とする苦情解決の相談制度が創設され、社会福祉事業者に対し苦情解決の責務が課されるとともに、苦情を受け付け、解決をあっせんする機関として、都道府県社会福祉協議会に「運営適正化委員会」を設置するとされた。 |
|
■ダイオキシン■ 岡村 県は、ダイオキシン類の発生源対策として、市町村のごみ焼却炉の構造及び維持管理について、指導の強化や廃棄物の野焼き対策等を実施した。 東城環境生活部長 平成12年度の環境調査は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、環境庁が定めた「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」に従い、県内では、昨年度より10地点多い86地点で調査を行っている。 岡村 環境調査結果を有効に活用し、ダイオキシン類の排出抑制対策を進めるべきと思うがどうか。 東城環境生活部長 環境調査結果を有効に活用するためには、関係自治体との情報交換を密にするとともに、広く県民・事業者に分かりやすく、かつ正確に情報を提供し、ダイオキシン類に対する理解を高め、家庭用小型焼却炉の使用の自粛、廃プラスチック類の除去等のダイオキシン類の排出抑制対策について協力を求めていくことが必要である。 岡村 ダイオキシン法に基づく大気基準適用施設の届出状況はどうか。 東城環境生活部長 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、県に届出された大気基準適用施設は、平成12年3月末現在、685施設である。 岡村 届出施設に対するダイオキシン類の指導はどのように行っているのか。 東城環境生活部長 県は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出施設に対して、同法に基づく立入検査を行い、廃棄物焼却炉設置事業者に対し、廃棄物焼却量、稼働時間等の運転状況の記録・保存、廃プラスチック類の除去等、排出基準の遵守に必要な施設管理に関する指導や排出ガスの自主測定の実施等について指導を行っている。 岡村 ダイオキシン類の健康影響については、世界保健機関(WHO)において、平成10年5月に、安全の目安となる1日当たりの摂取量の見直しが行われた。 梶水道局長 国は、平成11年12月に水道の水質基準を補完する項目として設定してある監視項目に、ダイオキシン類を追加し、健康への影響をもとに、指針値を1リットル当たり1ピコグラム以下とした。県営水道では、国の動向を踏まえ、平成11年度からすべての浄水場でダイオキシン類の検査を定期的に実施している。 |
|
■フロン対策■ 岡村 廃棄された冷蔵庫等から放出され、成層圏に達したフロンガスは、地上に降り注ぐ有害な紫外線を吸収しているオゾン層を破壊することが明らかにされている。 東城環境生活部長 フロンについては、主に家電製品、カーエアコン及び業務用冷凍空調機器に使用されているが、県内におけるこれらの機器からの平成10年度の回収状況は、県全体で約18トンである。 岡村 フロンの回収を促進するためにどのように取り組んでいるのか。 東城環境生活部長 本県のフロン回収の取り組みについては、家電製品、カーエアコン及び業務用冷凍空調機器等の業界ごとにフロン回収を推進するため、県、市町村及び各種団体で構成する「千葉県フロン回収処理推進協議会」において回収・処理システムを構築し、平成10年4月から組織的に回収を始めている。 |
|
■情報教育■ 岡村 児童・生徒があふれる情報の中で主体的に情報を選択活用し、情報の発信、受信の基本的ルールを身にづけることや情報化の影響等について理解を深めることは、学校教育において今後一層重要なものになっていくものと考える。 中村教育長 今後、高度情報通信社会がより一層進展する中では、すべての児童生徒が情報活用能力を培うことや情報化の影響等についての理解を深めることは大変重要なことである。 岡村 県教育委員会として、今後どのように情報教育に取り組んでいくのか。 中村教育長 県教育委員会は、指導者育成及び学校の情報環境整備の観点から、情報教育に関する各種研修講座の実施、情報処理技術者派遣事業、高等学校の教育用コンピュータ等の計画的な整備を行い、情報教育の推進・充実を図ってきたが、今後とも、情報環境のより一層の整備に努めるとともに、平成14年、15年度からの新学習指導要領に沿った新教育課程の円滑な実施に向け、高等学校の新教科「情報」の免許付与を計画的に進め、小・中・高等学校の指導者養成研修等を充実させ、情報教育の推進に努力していきたい。 |