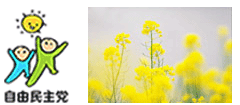議会レポート
平成10年9月
|
|

|
高齢者・障害者が安心して
歩ける歩道の整備を
|
■ダイオキシン■ 岡村 昭和47年に製造が禁止されたPCBは、処理方法が確立されず、現在まで30年近くにわたって産業廃棄物として保管することとされており、PCBもダイオキシン類と同様に有害で、継続的かつ適切な保管及びモニタリングが必要である。 白戸環境部長 本年5月に、スイスのジュネーブで開催されたWHO欧州事務局専門家会議において、ダイオキシン類にはコプラナーPCBも含めて考えるなどの見解が示された。 岡村 大気・水質等のダイオキシン類のモニタリングについて、その測定地点や測定回数の充実を図るべきと思うがどうか。 白戸環境部長 ダイオキシン類のモニタリングについて、今年度は、大気大地点で2回、水質・底質二地点、土壌二地点で各2回実施することとしている。 岡村 県と市町村が行っている大気モニタリングについて、市町村と十分な連携を図るべきと思うがどうか。 白戸環境部長 ダイオキシン類の大気環境モニタリングについて、県内の広域的な状況を把握することが有益であり、市町村と一体的に実施することが必要であると認識している。このため、県及び関係市で構成する「ダイオキシン類大気環境調査に係る調整会議」を設置し、この会議で協議した結果、同じ日に測定することや、測定結果の情報交換を行うことについて、原則として合意した。 岡村 県内におけるPCBの保管状況はどうか。 白戸環境部長 コンデンサーや変圧器等のPCB使用機器については、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物に指定されており、排出事業者には、同法の技術上の基準に従い、生活環境保全上支障がないように保管することが義務づけられている。 岡村 ダイオキシン類の排出抑制対策をさらに強化することは当然のことであるが、もっとさかのぼって、発生源から絶つ必要がある。 沼田知事 県は、ダイオキシン類の削減のため、広域化に向けたごみ処理施設の集約化を図る市町村間の調整は、大変重要であると認識している。 岡村 野焼きの中止指導をさらに強化すべきと思うがどうか。 白戸環境部長 野焼きは、煙や悪臭のほか、ダイオキシン類による汚染のおそれもあることから、県は、現地に立ち入りを行い、野焼き行為者に対し、口頭や文書により中止や適正処理の指導を行っている。 岡村 「小規模廃棄物焼却炉等に係るダイオキシン類及びばいじん排出抑制指導要綱」の周知徹底をどのように図るのか。 白戸環境部長 この指導要綱は、小規模廃棄物焼却炉の設置者に対して届け出を義務づけるなど、新たな規制処置を講ずるとともに、一般家庭の焼却炉についても使用の自粛を求めていることから、県民一般に対して広く周知することが重要と認識している。 |
|
■廃棄物■ 岡村 環境問題は今日、生産、消費、廃棄のプロセスの中で、物を燃やして二酸化炭素を出すこと自体を問われる地球的な問題にまで拡大してきている。このため資源を過度に消費する社会経済システムを見直し、循環型社会を目指すことが必要である。 白戸環境部長 平成8年度の一般廃棄物の総排出量は208万9千トンであり、そのうち市町村で処理された事業系一般廃棄物は、約3割に当たる55万9千トンである。 岡村 県では、事業系一般廃棄物の減量化やリサイクルの推進のため、どのような取り組みを行っているのか。 白戸環境部長 事業系一般廃棄物は自己処理が原則であるが、市町村は生活系一般廃棄物の処理に支障を来さない限りにおいて、有料で処理している。 |
|
■介護保険制度■ 岡村 要介護認定は、調査員の調査結果を、コンピュータに入力して行う一次判定と、その判定結果とかかりつけ医師の意見書をもとに行う介護認定審査会による二次判定により行われる。 荒社会部長 要介護認定は、介護保険に基づくサービスの必要度を客観的に確認しようとするものであり、介護認定審査会での審査判定は、全国一律の客観的な基準である要介護認定基準に照らして行うこととなっている。 岡村 心の通ったホームヘルプサービスを確保するため、ホームヘルパーの資質の向上を図る必要があると思うがどうか。 荒社会部長 痴呆のある高齢者について、コンピュータによる一次判定で要介護度が低く出るという報告は、本県の昨年度のモデル事業実施地域からも多く出され、県としてもその旨を国に報告した。 岡村 痴呆の要介護度が軽く判定されるという昨年度の要介護認定モデル事業の意見について、本年度はどのように反映されているのか。 荒社会部長 介護認定審査会は保健、医療、福祉分野の学識経験者から構成される合議体で、おおむね5名の委員によって審査判定がなされることとされている。介護認定審査会の一回の開催での処理件数にはおのずから限界があることから、高齢者が多く、要介護認定の申請も多く見込まれる市などについては、一つの審査会のみですべてを処理することは困難である。このため複数の審査会の設置を可能とし、その数については、各市町村ごとに申請件数見込み及び一カ月当たりの開催回数見込みをもとに必要数を算定できるようにする方向で、国において検討が進められている。 岡村 市町村における介護認定審査会の設置数の考え方はどうか。 荒社会部長 ホームヘルパーは在宅介護サービスの中核的担い手として重要な役割を果たしており、その資質の向上は、介護保険制度導入後においても、継続的に取り組まなければならない課題であると認識している。 |
|
■福祉のまちづくり■ 岡村 県では、高齢者や障害者等を初め、だれもが住みよい福祉のまちづくりを実現するため、平成8年3月に千葉県福祉のまちづくり条例を制定した。 沼田知事 県の公共施設は模範になる施設となるべきであり、県としても努力している。 岡村 県が管理する歩道の整備は、どのような方針で進めているのか。 池尻土木部長 歩道の整備を進めるに当たっては、高齢者や障害者等を含め、すべての人が利用しやすい施設とすることが必要である。 岡村 歩道の整備は毎年どの程度行われているのか。 池尻土木部長 歩道の整備については、毎年度、用地費を含め約75億円前後の事業費により整備を進めてきており、毎年平均約20キロメートルの供用が図られている。 岡村 だれもが利用しやすい鉄道にするため、一つでも多くの駅にエレベーターやエスカレーターの整備を促進すべきと思うが、県はどのような支援策を講じていくのか。 荒社会部長 鉄道駅は、県民の移動手段として重要な公共交通機関の一つであるが、駅の階段が、高齢者や障害者等にとって、大きな障壁になっており、この改善策としてエレベーターやエスカレーターを設置する鉄道事業者が増えてきている。 |
|
■雇用■ 岡村 長引く景気の低迷により、我が国の雇用情勢は極めて厳しく、とりわけ障害者については、一たん離職すると、その再就職が容易でないという状況の中で、より効果的な雇用対策及び雇用環境の整備が必要と考える。 内田商工労働部長 本県における平成9年6月1日現在の状況は、実雇用率1.42%、雇用されている障害者数3833人で、前年より42人増加した。 岡村 不況の中であるが、障害者の雇用を促進するため、どのような対策を講じているのか。 内田商工労働部長 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正により、本年7月1日から、算定基礎に知的障害者を加えた新たな法定雇用率が設定され、一般民間企業については、1.6%から1.8%に引き上げられた。 岡村 一般企業に雇用されることが難しい比較的程度の重い障害者の福祉的就労の場である授産施設等の整備状況は、どのようになっているのか。 荒社会部長 福祉的就労の場としては、定員・職員配置・施設等の基準が法律等で定められている授産施設と、おおむね授産施設よりも小規模な福祉作業所がある。 |