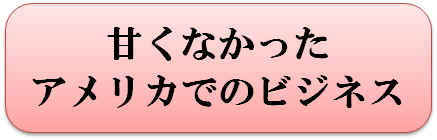
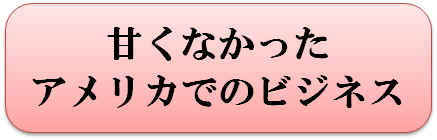
アメリカの市場は大きい。世界の消費経済の30%を占めている。人口は日本の2.3倍だから営業効率はかなり良い。アメリカで開発された製品を高い特許料を支払っても、日本の高いもの真似技術と効率的な日本の生産技術を使えば、開発費は要らないし、関税の自由化でアメリカにもって行けばどんどん売れる。こんなに日本の製品が売れるのだから、現地で生産すれば、輸送賃がなくなり、生産規模の拡大でさらに製品は安くなり、膨大な利益が生まれるはずだ。少々の言葉の壁など、ものづくりは人間をあいてに仕事をするのではなく、ものが対象なのだから、技術さえしっかりしていれば、そして、その技術の管理がしっかりできていれば、何の問題もなかろう。それでも、多少の日常会話ぐらいはできなくては困るだろうから、短期に英会話の訓練くらいはさせて、アメリカに技術屋を送り込め、という具合で、日本のメーカーのアメリカ進出が始まる。(「本社の誤解」から)
| 本社の誤解 |
勝手は、海外勤務は出世コースであった。ところが、実際にアメリカでものづくりを始めると、なかなか思うように利益が上がらない。そして、事務屋さんが、いまや外国は決して遠くないというようなことを言い出し、なにも海外勤務手当てなど不要とのことで、本国の給与にすこし色をつけたぐらいの給与で、社員を海外に派遣する時代になった。 では、一体、どこに日本の本社の誤解があるのだろうか。 |
||
| アメリカでのビジネス 甘くない | アメリカでのビジネスの難しさ | 知ってビックリ。これが当たり前。日本と違う。 | パワーポイント 要約 |
| アメリカのビジネス 甘くはなかった その1 | 「日本停滞の最大の理由はグローバル化の失敗だ」。その原因のひとつにあるのは、「日本人の異文化交流の苦手さだ。国内の文化的差異が小さいためか、日本人は異文化との積極的な交流を避ける。せっかく、MITやハーバード大学に留学しても同国人で固まっているのでは、何にもならない。」( 日経新聞、2010, 10, 22 ) だ | 1.初めに | |
| 2.タブー | |||
| アメリカのビジネス 甘くはなかった その2 | 3.アメリカのサラリーマン気質 |
||
| 4.サラリーマン根性(?) | |||
| 5.アメリカ人に欠けているもの |
|||
| 6.まとめ | |||
| アメリカのビジネス 甘くはなかった その3 | ソーティング会社の話 |
||
| 市民権の話 |
|||