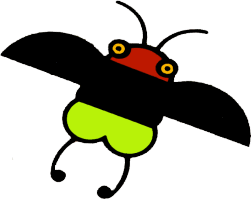
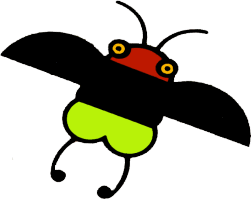
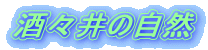
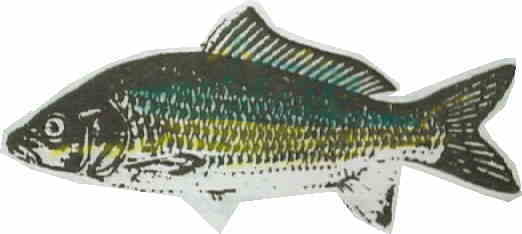 |
 |
| 鯉 大きい物は80センチをこえまます。 印旛沼水系ではよく見れます 釣りをしても楽しいです。 |
ドジョウ 産卵は5〜6月。 腸で呼吸をしています 時々、水面 に呼吸をしに上がってきます。 泥の中に居るので見つけるのが 難しい。 |
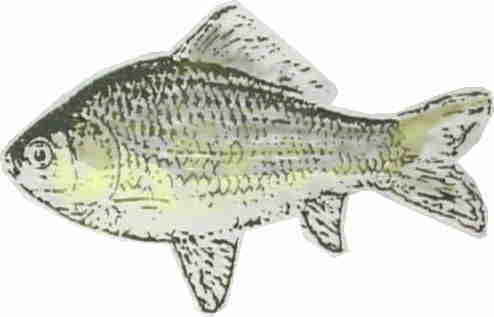 |
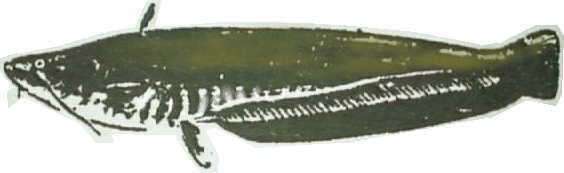 |
| フナ キンブナは背が低く、黄褐色。 15センチと小さい。砂泥底で 水草のあるところにいる。 ギンブナは、もっと大きくなり、 マブナとも呼ぶ。 背の高い、30センチをこえるヘラ ブナは植物プランクトンを食べる。 |
ナマズ 普段あまり見れないが、北印旛沼 で一度釣れたことがある。2対4本 のヒゲがある。 いつも底でジットしている。地震 の7〜8時間前から盛んに動き出 すのはそのせいかな。 食用に使われています。 |
 |
 |
| メダカ 水田の水路、沼池にはたくさん 見れたが、この10年ぐらいで、 ずいぶん減ってしまいました。 鳥、外来魚、農薬、コンクリー ト水路とメダカの敵が多いのです |
カダヤシ 見た目はメダカに似ていますが、 グッピーの仲間です。 特定外来生物に指定されているので、 勝手に持ち帰ったり、飼育、放流は 出来ませんので気を付けましょう。 メダカとの大きな違いは、尾ビレの形 です。メダカは、上下が角ばってい ますが、カダヤシは、丸みを帯びてい ます。ここ数年、印旛沼水系に繁殖し ていますので、気を付けましょう!! |
 |
 |
| モツゴ 水路、中川、どこでも見られる魚。 釣りでも釣れます。 クチボゾとも呼んでいます。 受け口のおちょぼ口である。 体側に口まで黒い帯がある。 |
タモロコ: 田植えの時期になると水路から水田に 移動して繁殖。尻尾からエラにかけて 黒い側線がある。 コイ科の愛嬌のある丸い口とヒゲが特徴。 雑食性で集団で群れを作り、水深の深い 場所を泳ぐ。 |
 |
|
| クルメサヨリ 数年前に北印旛沼に入る利根川 につながる川で見ました。 川にサヨリがいるなんて! 淡水のサヨリなんですね。 珍しいです。 |
雷魚(ライギョ) 名はカムルチー。タイワンドジョウの 仲間で輸入されました。 6〜8月に北印旛沼のヨシのあると ころで見かけます。60センチ以上の 大きなものを見たことがあります。 肉食です。 |
 |
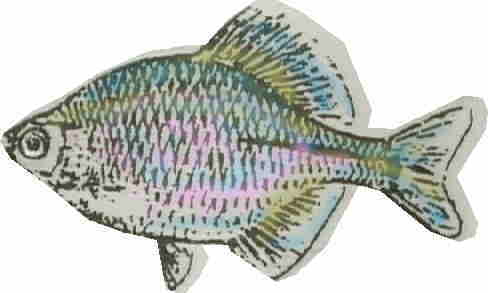 |
| ワタカ 琵琶湖水系からやって来た魚で。 中央水路、印旛沼水系の少し流 れがあるところに群でいます。 植物性プランクトンの他動物性 のものも食べます。 つかむとキューと鳴くので、 逃がしてやります。 |
タイリクバラタナゴ 中国から入りました。 10年ぐらい前は、どこでもいたので すがだいぶ数が減りました。 色がきれいで、淡水二枚貝の中に 産卵します。この貝がいなくなると、 タナゴもいなくなってしまいます。 |
 |
 |
| ブルーギル 印旛沼、周辺の水路、他。 北アメリカから来た魚。20センチ まで大きくなる。 小さい魚などを食べて大きくなり、 繁殖力が強い。 |
オオクチバス ラージマウス、ブラックバスとも呼ば れる。 北アメリカから来た魚で、60センチ をこえるものがいます。 印旛沼水系、中央水路にいます、 減少しています。小魚、小動物を食 べてます。 |
| <釣りの注意> 1, ブルーギル、オオクチバスは小さな 魚をたくさん食べてしまいます。 釣った時は、持ち帰って他の川や池に はなしてはいけません。 2,釣り糸をすてると、その糸に鳥の足が からまって、足が切れてしまいます。 3,釣り禁止の場所は、目に見えない 水面の下の流れ、水温、障害物などが 危険なんです。 釣りはやめましょう! |
|