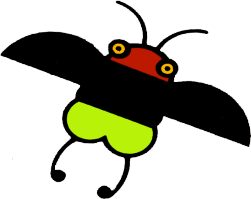| 1,旧宿場街道コース(酒々井旧街道へ): 酒々井役場から出発して旧国道51号沿い を探索します。 昔の宿場町としての”街道の木”を感じます。 酒々井役場: 酒々井町は明治22年に出来た町で すが、この役場の木も立派です。 ケヤキ、クス、ヤマモモの3種の木が 主に育ってます。まだまだ、大きくなる 木ですね。木陰も風が通って気持ちが 良いのですが、ベンチが欲しくなります。 |
 |
| 酒々井東光寺:(しすい とうこうじ) 大廣山密蔵院東光寺。 本尊は胎蔵界大日如来 (たいぞうかいだいにちにょらい) 境内に幕末の書道家で寺子屋を 開いた高幡南渓の墓がある。 入り口の大木が古さを感じます。 |
 |
| 朝日神社: 神社の建物は小さいのですが、 ケヤキの木は大きいです。 |
 |
| 旧酒々井郵便局跡: 酒々井の台地(仮名)で最も高いケヤキ ですね。 酒々井町の自然物の中では、最も 高いところに位置するのでは。 街道からこの木を目指せば酒々井 宿場に必ず着く、と言った感じです。 まっすぐ素直に伸びた”高木”です。 これは、太陽が均等に当たったせい かも知れませんね。 |
 |
| 酒々井麻賀多神社: (しすい まかたじんじゃ) 酒々井の鎮守。千年以上前に建立 されたと伝わります。 祭神は稚産霊命(わかむすびのみこと)。 安政六(1859)年、江戸で作られた山車 (だし)人形は小野道風。 名人三代目仲秀英(なかしゅうえい)の作。 この境内のケヤキの密度は凄いです。 薄暗く、”木の精”を感じます。 |
 |
築山:(つきやま) 通称「桜山」。明治天皇巡行の記念碑が 建っています。 大きな木は無いのですが、カシ、シイの 仲間が多いです。 印旛沼、筑波山を眺望できる、名勝地です。 ”風の木々”を感じます |
 |