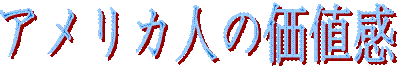
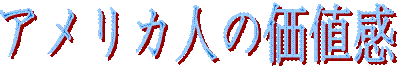
その背景にあるもの
1.
はじめに 1
アメリカ人はどう思っているのか
もともとは、インディアンの国だ
3.
先住民アメリカ人の価値観
8
インディアンの価値観
伝説に見るインディアンの価値観
4.
西洋人社会の価値観
16
アメリカにおける西洋人の歴史
5.
多民族国家の価値観
24
民族による価値観の相違
価値観の裏にあるもの
宗教の力
6.
西洋人とインディアンの価値観の融和
27
ルイスとクラークの冒険について
ルイスとクラークの冒険が果たした役割
アメリカ経済の破綻
アメリカは立ち直れるか
8.
最後に
40
1.はじめに
1970年代、石油ショックのときに日本の産業にとって欠くべからざる原材料のコストが大幅に上がり、日本でものづくりをすることが難しくなりました。そこで、安い人件費の東南アジアや、中国、そして、大消費地であるアメリカやヨーロッパで直接ものを作らざるを得なくなりました。こうしたことを背景に当時、よくささやかれた言葉は、「ビジネスのグローバル化」ということでした。
しかしながら、日本人がビジネスのために海外に出て行くことには、大変な障害があります。それは言葉の問題です。ということで、日本人ビジネスマンが国際社会で活躍するには、どうしても克服しなければならない、この言葉の問題が大変クローズ・アップされました。ところが、日本人が海外に出て、本当に苦労するのは、ただ単に言葉の問題だけでないのです。言葉の問題より、もっと深刻なことは、日本人の常識、日本人的考え方が海外ではなかなか理解してもらえないことです。私達が、日本で生活するのに当たり前のこと、日本人なら、誰もが理解できることが、海外では、必ずしも当たり前ではないのです。たとえばこんな例があります。われわれは、仕事の効率を高め、少しでも、利益を上げようと汗水流して頑張ります。しかし、ヨーロッパ人やアメリカ人は、効率を上げることが必ずしも美徳であるとは思って居ないのです。それよりも、精神的にゆとりのある生活のほうが大事だと考えています。人生をどのように送るかを考えるとき、かれらの持つ価値観と、日本人の持つ価値観が全く違うのです。議論しても始まらない、そして、いつも問題を先送りしてきたこの問題。では、われわれは、そのような人たちと一緒に仕事をするときに如何すればよいのでしょうか。
こんなことを常日頃考えていた私は、30年余り勤めた大手企業のサラリーマンを退職し、しばらく中小企業の部品メーカーで働いたあと、自らアメリカに職を求め、価値観の違いを現実に体験することにしました。若い人たちに、どんどん海外にでて、自分の実力で、仕事をばりばりとやってほしいと思っていましたので、そのためにはなにが障害になるのかを実際に体験してみたかったからです。
アメリカには、四年半滞在することになりました。それ以前に、長期の派遣で約半年程生活したことがありましたので、都合、5年程のアメリカ生活でした。この間に感じた、アメリカ人たちの価値観について、その裏にあるもの、そして、彼らの考え方について、実際の体験から分析し、その価値観の違いをどう克服していけばよいのかを考えてみたいと思います。
1.
アメリカ人って誰のこと
われわれは一口にアメリカといいますが、では、アメリカと言う国はいったいどんな国でしょうか。まず、国の広さ。これは、日本の26倍と言われています。そして、人口は、2億8千万人、日本の人口の約2倍です。しかし、アメリカという国は、われわれが思っている以上に複雑な事情があります。まず、第一に、この広さですが、アメリカ大陸は、東西に3,000マイル(
5,000 km)、そして、南北に2,000マイル(
3,200 km)です。これは、日本の稚内から鹿児島までが、JRの距離で2,000
kmということから考えると、途轍もなく大きな国であることが分かると思います。そして、大陸のなかには、48の州がありますが、アメリカは、実は、こうした州の寄り集まり、合衆国なのです。各州には独自の法律がありますし、税金も全く異なります。つまり、われわれが考えている以上に、これらの州は自治権が強く、ほとんど、独立国と同じです。さらに複雑なのは、ここに住んでいる人たちは、決して、1つの民族ではなく多種多様です。アメリカという国は、16世紀に西洋から白人が移住してきて、独立した国です。かれらの母国も、1つではありません。それもさることながら、アメリカにはもともと何百部族という先住民族が住んでいました。ですから、ここに住んでいる人たちは、まさしく、一言で、なに人と言うわけには行かないのです。統計では、ドイツ系の白人が一番多く、42,800千人、ついで、アイルランド系の白人か、30,520千人、アフリカ系黒人 24,900千人、イギリス系白人 24,510
千人、以下、カリブ・アメリカ人、メキシコ人と続いています。そして、先住民族のインディアンは、7,880千人です。単一民族にすると、日本よりも人口は少ないのです。
このように多様な人種の人たちが共存しているわけです。共存と言う言葉が適当であるかどうかは分かりませんが、しかしながら、ここでは、人種による価値観、宗教に基づく価値観など、実に沢山の価値観、つまり、ものの考え方、もうすこし具体的にいえば、自分の人生にとって大事なもの、そして、なにが自分達が生き残っていくために必要かということが、別々なのです。ですから、一概にアメリカ人といっても、どんな価値観を持っているのか、何を考えて毎日をおくっているかは、千差万別といっても良いのではないでしょうか。それでも、アメリカは、合衆国として世界の平和の維持と、経済をリードしています。いったい、国家に対する彼らの求心力とは何なのでしょうか。
アメリカ人は、どう思っているのか
かって私は、サンフランシスコの郊外のまち、リバモアの人たちとボーイスカウトの国際交流をしたことがあります。リバモアというのは、日本で言えば、丁度、つくば学園都市といったところです。アメリカ全土、各地から、優秀な研究者が集まって国家レベルの研究をしている人たちの町です。大学の教授から、国立の研究所に勤めていた人たち、そして、世界中にあるアメリカの軍の研究施設からの派遣者達でした。ですから、彼らはアメリカの中でも超一流の知識人たちと言えましょう。そのなかのある人に尋ねたことがあります。「アメリカ人って、一体誰を指していると考えていますか?」と。すると、即座に返ってきた彼の答えは、「アメリカ人だって?、そんなこと、一口では言えないさ。でも、自分たちは、アメリカを良くしようと思って税金をしっかり支払っている人がアメリカ人と思っているよ。」と言う返事でした。これを聞いて、なるほどと思いました。彼らは、肌の色や、しゃべる言葉、そして、宗教は違っていても、アメリカを自分達の国と思い、そのアメリカを良くしようと考えている人、そして、そのためにしっかりと税金を納めている人、それがアメリカ人と言うわけです。これを聞いて、ハッとしました。アメリカの大きな市場を目当てに日本から沢山の企業がアメリカに進出してきているのですが、そのほとんどは、アメリカで利益を上げて、それを日本に持ち帰ろういう企業ではないでしょうか。それでなくても、税の優遇措置を受けて、あるいは、なにやかやの経費の名目で日本の親会社に支払いをして、決済のうまいからくりで税金をできるだけ低くして利益を上げようとしている日本の企業がありはしないでしょうか。こういう日本の会社に対して、彼らはどんな思いで見ているかは想像に難くないと思います。
様々な人種の人たちが、広い大地で生活をしています。人口密度は、平均で日本の1/10以下です。また、住民は東西の沿岸地方に集中していますから、中西部では、数十分の一ではないでしょうか。沿岸地域の人口密度の高いところ、そして、大都市では、様々な人たちが、様々な国や州から集まってきていますので、彼らは取り立ててだれがアメリカ人だなんていうことを意識することはあまりないと思います。しかし、中西部になると、全く様相が変わります。ご存知のように、アメリカには先住民といわれるインディアンがいました。ここに白人達が入ってきたのは、19世紀になってからです。ですから、この大陸には、アメリカとしての歴史は、高々200年しかないのです。その歴史は、この地の自然と気候と、先住民との主権争いで、それは、まさしく過酷であり、また、辛い思い出の日々でありました。自分達の生活の場を求めて、もともとは裕福でない東部の人達、そして、ヨーロッパから新しく移住してきた人達が、中西部に入植したわけですが、そこは、雨もふらず、木々も十分に育たない、やせこけた砂岩の台地だったのです。当時は満足な道具もありませんでしたので、なにをするにも人手で、汗を流してやるしかありませんでした。ネブラスカのBeatriceと言う小さな田舎町に、リンカーン大統領が指定した、入植者達の当時の家が大事に保管され、国立の歴史館とて残されています。当時の様子を後世に伝えるために建てられたものですが、そこには、当時の生活をしのぶ沢山の日用品が展示されています。主婦が馬の代わりに鋤を引っ張りました。鍬のないときには、手で土を起こしました。最初は住む家を建てる木さえありませんてしたので、土を掘って、草で屋根を葺き、動物達と同じように穴のなかで生活をしていたそうです。しかも、そうした土地は、合衆国政府から所有権を認められていたとはいえ、もともとはインディアン達が住んでいた土地なのです。そのインディアン達を強制的に移住をさせたのは、それからまだ先、数十年後のことです。ですから、インディアン達はまだ自分達の生活の場として、この平原で暮らしていたのです。当然のことながら、両者の間で争いが耐えませんでした。自らの身は自らが守る以外にはないというのが、当時の未開地の状況です。西部劇のなかに、白人の牧場がインディアンに襲われ、焼き払われて、女子供が略奪されたなんていうストーリー映画がありますが、それが、まだ、ほんの百年前のころ、起きていたわけです。ですから、ここに入植した白人達は、土地の開拓とわが身の安全を、インディアンと必死で戦いながら確保してきたわけです。現代の人達にしてみれば、ここは、曾おじいさん、曾お婆さんたちが、顔がしわくちゃになるまで頑張って築いてきた土地なのです。そこがもともとインディアンの土地であることは重々に知りながらも、かれらは、自分達が命を掛けて築いてきた新しい祖国なのです。ですから、まさしく、自分達がアメリカ人であり、ここは、自分達が作り上げた祖国だという意識が非常に強いのです。自分が育ったところは、大きな牧場で、何百等の牛と一緒に暮らしていたというような人ばかりです。そうした人達の間には、まだ、歴然と人種差別と言う意識が消えずに残っているのです。いまだに、中西部は荒地のまま残っているところが随分あります。とはいえ、南部から流れてくる、黒人達の入り込む余地など全くありません。東洋人も沢山やってきますが、活躍する場はとても限られているのです。こうして、ここにはいつまでも白人の開拓精神がまだ色濃く残っている土地なのです。
これは、極端な例かも知れませんが、私の居たネブラスカの州都リンカーンのなかのちょっとしたレストラン、ここには、白人以外のウェートレスはほとんど居ません。こうしたお店に来る人達が、白人以外の人から給仕をされることを嫌がるということをレストランの経営者は良く知っているからです。賃金格差があるのかもしれませんが、白人以外の人が働くお店の格はやはり低いのです。また、テレビのコマーシャルにしても同じような目で見ていると、潜在的にそんな気持ちが働いていることが良く分かります。ここには、なくなった筈の人種差別はまだまだ現存しているのです。
もともとは、インディアンの国だ
中西部にいるアメリカ人といえば、黒人の人口は非常に少ないし、また、ヒスパニック系の人もいないわけではありませんが、テキサスやカリフォルニアと比べれば圧倒的に少数民族です。ただ、問題は、この地がもともとは、インディアンの土地だったことです。アメリカの州の名前の半数以上がインディアンの言葉から来ているものです。つまり、そうした土地に、インディアンが何百年も前から自然とともに生きてきていたわけです。ネブラスカは、「平らな川、広い川」というインディアンの言葉から来ています。オハイオは、「大きな川、美しい川」、コネティカットは「長い川のほとり」、イリノイは「男ども」の意味です。ミシガンは「大きな湖」、ミネソタは、「空の色をした水」ミズーリは「大きなカヌー」と言う意味だそうです・カンザスは、「南風の人」テネシーは、チェロキー族の言葉で「大きく曲がった川」などなど、こうしてみると、現代人でも、自分たちの州の名前を口にするたびに、ここは、元来、インディアン達の生活の場であったということに気がつきます。
そこで、調べてみましたら、なんと、アメリカの大陸には、もともと数百もの部族がいたとのことです。勇猛果敢なスー族やクロー族。西部劇で活躍するアバッチ族やシャイアン族。ナバホ族はアリゾナからニューメキシコにかけて最大の居留地を持っています。そのほか、コマンチ、アラパホ、チェロキー、ポンカ、ショショーネ、タタンカ、などなど、われわれ西部劇に親しんだ世代には懐かしい名前が次々に出てきます。それだけでなく、田舎の都市の名前にインディアンの部族の名前がついた町が沢山あります。カンザス、スー、プエブロ、オマハ、シャイアンなどの大都市、それらに加え、無数の田舎の町があります。もちろんこうした地域は、今でもインディアンの文化が脈々と引き継がれているのです。
しかし、彼らが、今のように居留保護区のなかで生活をするようになった裏には、大変な悲しい物語があります。これはアパラチア山脈の、今でいうスモーキーマウンテン辺りに住んでいたインディアンチェロキー族の物語です。
このグレートスモーキーマウンテン。アメリカが誇る自然の動植物の宝庫。その紹介パンフレットにはこんなことが書いてあります。
世界中で、このスモーキーマウンテンに匹敵する、動植物の豊富なところはほかにない。北ヨーロッパの森に比べて優れているのは、ここには、1500種類以上もの植物、そして、数十種類の天然の魚、200種類以上の野鳥、それに、60種類の動物達が生息して居る。こうした、天然の宝庫は、現在、世界遺産に指定され、その保護が進められている。
もともと、この地に生活していたCherokeeは、ここを彼らの言葉の意味で、
“煙のような、緑の地
”を意味する“shaconage
”と呼んでいました。彼らはこの地に農場を開拓し、ログハウスを建てて、そして、ヨーロッパ人が入植して来たときには、彼らは融和する方針で受け入れてきたのです。しかし、冨を優先するヨーロッパ人は、彼らの土地を奪ってしまったのです。1790年代に白人達の入植が始まり、彼らを追いやりはじめ、そして、チェロキーは中西部へと強制的に移住を強いられました。過酷な旅を強いられた彼等は、出発する時には1
万数千人いたのが、キャンプに到達したときには、その1/3は、死んでしまったということです。これが有名な「涙のトレイル」となって今に伝わっています。一部のチェロキー族はこの山奥に逃れてここに残り、この地で生活を続けましたが部族の殆どは、現在のオクラホマまで連れて行かれたのです。それは、1830年代の頃のことです。
同じような悲劇は他にも沢山あります。
ネブラスカ・ポンカ族の話
1700年代の初めに、ポンカ族は彼らの故郷サウスダコタからネブラスカにやってきました。1877年になり、政府はポンカ族の酋長をオクラホマのインディアン保護地域に視察に送りましたが、酋長はその土地があまり気に入らなかったのです。しかし、彼がふるさとに戻ると、部族の大部分のものは、すでに移住をする用意を済ませているという状態だったのです。オクラホマに彼らが移り住んだのはよいのですが、しかし、彼らはそこで食料を手に入れることができず、部族の沢山のものが病気で倒れてしまい、部族の1/3近くの人が亡くなってしまいました。酋長のスタンディング・ベアの息子が亡くなると、彼らの一族は、その体を密かに、ネブラスカに運び、神聖なる地に埋葬しました。インディアン達は、居留地から出ることを認められていなかったので、彼らは、裏切り者として取り扱われるようになったのです。そして、スタンディング・ベアと彼の一族が自由になるにはそれから何年も掛かったのです。1881年になり、ネブラスカにあった彼らの故郷の地が彼らに返還され、部族の一部はネブラスカに戻りました。そして、今日、ネブラスカ・ポンカの本拠地がネブラスカに置かれるようななったのです。
Wounded
Knee (
South Dakota ) の大虐殺
このインディアンの虐殺については、こんな解説があったので紹介します。
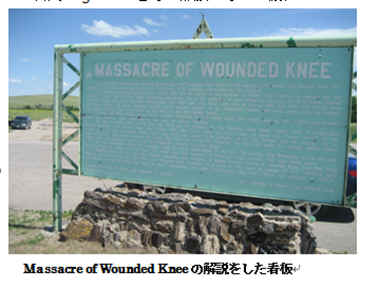
1890年の12月29日の朝に、Sioux
の酋長Big
Foot とその部族のもので彼についてゆくもの350人がWounded
Knee Creekの土手にキャンプを張っていました。彼らの周りをアメリカ騎兵隊が取り囲み、Big
Foot の逮捕とかれの戦士達の武装解除を迫っていました。状況は非常に深刻でありました。いざこざが何ヶ月もの間続いていたのです。
Ghost
Dance の願い
以前に、誇り高きSioux族は、自分たちのどこにでも自由にいくことができる生活が破壊され、バッファローがいなくなり、そして、自分たちが生きていく間は、インディアンの統治官に依存して居留地に拘束されるということに気づきました。かっての栄華の日々に戻ろうという絶望的な挑戦のなかで、たくさんの人々が、Wovokaという教条的な祈祷師の神秘的な新しい予言に救済を求めたのです。South
DakotaのSioux族の使節がNevadaまで、かれの言葉を聞くために旅にでました。Wovokaは自分自身のことを救世主と自称し、死というものこそ、インディアンたちがたくさんの狩猟をしながら生活をすることのできた古い時代にもどることが出きる道であると予言しました。新しい土地の潮のような波が大地を覆い、白人達を埋葬し、そして、もとの大平原に戻すことができると予言したのです。そのようなことが現実になるように、インディアンたちは、Ghost
Danceという踊りを踊ることにしたのです。たくさんの踊り手が、ワシやバッファーをイメージするように飾られた、色とりどりのきらびやかな衣装をまといました。彼らは、この“Ghost
の衣装”が、自分たちをあの青白いメッキの弾丸から身を守ってくれるものと信じていたのです。そして、1890年の秋には、このGhost
Danceは、Dakotaの居留地の中にあるSioux族の村の間に広まってゆき、それが、インディアンたちを勇気づけ、白人達に恐怖を与えるようになっていったのです。絶望的になったPine
Ridgeにいたインディアンの統治官はワシントンにいる彼の上官に、次のような電報を打ったのです。”インディアンたちは、雪のなかで踊り狂い、野蛮で、狂っています・・・。われわれは防衛策が必要で、しかも、それはいますぐに、です。指導者を逮捕する必要があり、事態が収まるまでどこか軍の施設に拘束すべきです。これは、今すぐに実行すべきことです。“ そして、Standing
Rock 居留地にいる酋長のSitting
Bullを逮捕するようにとの指令が出ました。Sitting
Bullは、12月15日の襲撃で殺されると、次に目標になったのは、酋長のBig
Footだったのです。
かれは、Sitting
Bullの死を知り、Big
Footはかれの部族の人をPine
Ridge居留地に安全な場所を求めて南に移動をさせました。軍は12月28日にこの集団を拘束し、彼らをWounded
Knee のはずれに連れてゆき、そこでキャンプをさせたのです。次の日の朝、肺炎と乾燥で苦しんでいた酋長は、自分の部下の戦士達の真ん中に座り、そして、軍の指揮官と協議をしました。と、突然の朝の薄明かりの中に銃撃の音が鳴り渡りました。数秒間の間に積もり積もった思いがいきなり爆発したのです。インディアン達は取り上げられたライフルを取り戻すために走り回り、一方、軍は、Siouxのキャンプに容赦なく一斉射撃を加えたのです。高台からアメリカ軍のHotchkiss砲はブドウ弾をインディアンのテント小屋に機銃掃射したのです。男、女、そして、子供たちが逃げ回るなか、砲弾の煙が当たりに充満していました。多くのものが、まるで十字砲火を見下したように打たれることを承知でキャンプの隣にある峡谷のほうに逃げてゆきました。
やがて、銃弾の砲火が収まり煙が晴れ渡ると、なんとその場所には、酋長のBig
Footをはじめ、300人ものSioux族の人たちが死んでいたのです。騎兵隊のほうは25人の犠牲者が出ました。残されて騎兵隊が死者の片付けという過酷な仕事につくと、おりしも北からの強烈な厳しい寒波がやって来たのです。数日後に彼らはこの事件の後始末を完了しましたが、しかし、このWounded
Kneeで起きた虐殺は、あのGhost
Danceの運動を完全に抹消し、インディアンの抵抗戦争を終末に導いたのです。
大虐殺は、Wounded
Kneeだけではありませんでした。カンザスでも、Kidder
Masacreという事件がありました。でも、こうしたHistoric
Siteを訪れる白人の数はほんのわずかです。否、あえて知りたくないというのが事実だと思います。
オクラホマと言う州の名前は、チョクト族の言葉で「赤い人々の土地」という意味です。そして、西洋人たちがアメリカの中央大平原に入植してきたときに、沢山のインディアンの部族がここに強制的に移住をさせられた土地でもあります。そこには、ポンカ族のような悲劇の物語が沢山残っています
2.
先住民アメリカ人の価値観
インディアンの居留保護地域というのをご存知だと思いますが、では、一体、アメリカにはどの位の保護地域があるのでしょうか。
ここは、合衆国の政府により定められたアメリカ先住民部族により治められている地域なのです。現在、アメリカには、550以上の先住部族がいるといわれています。いわゆるインディアンの部族がこれだけあり、アメリカ中に、310地域の居留保護地域があるとのことです。これらの居留区の広さは、合計すると55.7million
エーカーあり、アメリカ全土の2.3%に当たります。そして、12のインディアン居留地は、ロード・アイランドの広さ(
776 エーカー
)より広いそうです。この地域では、インディアン部族の協議会が連邦政府に変わって統治しているのです。つまり、ここは自治区なのです。有名な居留地は、アリゾナにあるナバホ居留地。ここは、アメリカ最大の居留地で、強い自治権を持ち、一つの独立国家にも等しい力を持っています。有名なモニュメントバレーもここにあります。このナバホ族は、独自の言葉を持っており、その語尾変化に独特のものがあることから、第二次世界大戦では、この言葉が暗号に使われました。軍の指令文は、ナバホ語に翻訳され、これが受信されたあと、再び、ナバホ族出身の兵士により英語に戻されたそうです。この暗号は当時の日本軍は全く解読が不可能だったそうです。
ただ、こうして、インディアンが自ら統治しているというと、彼らには自由が保障され、豊かな生活を営んでいるかのごとく思われますが、果たして実際はどうでしょうか。アメリカをドライブしていて、沢山のインディアン居留地の中を走り回りましたが、どこもインディアンの居留地に入ると、それまでの白人の住んでいる地域とは周りの景色が一変します。土地は開発されておらず、また、住宅も貧相なテラスハウスが点在しているだけ。土地がやせている証拠で、ここでの経済的な自立は到底不可能と思われるようなところばかりです。農場を開拓するにも、また、牧場を経営するのにも、アメリカでは規模が大きく、膨大な資金が必要となりますが、彼らには、その元手がないのです。今では、政府により生活保護を受けて細々と生計を立てているのがやっと。失業率が高く、というより、産業がほとんどありませんから、かれらは、日雇いで白人の経営する農場や牧場に出稼ぎにいくくらいしか収入源がありません。その結果、彼らは酒におぼれ、麻薬に染まっていくのです。
しかし、インディアンがもともとこんな生活をしていたのではありません。チェロキー族はもともとアパラチア山脈の南部に住んでいました。しかし、ここに、金鉱が発見され、そのほか鉄鉱石や石炭が埋蔵されていることが分かると、アメリカ合衆国政府は、彼らに代替地としてオクラホマの地域をインディアン居留地として定め、彼らにここに移住することを求めました。チェロキー族は、ほとんどが反対をしたのですが、武力に勝るアメリカは彼らを強制移住させました。そして、移住のために集められた、17,000人のチェロキー族は、この旅の途中で4,000名以上が病気で亡くなったのです。チェロキー族の言語で、この出来事は、「われわれが泣いた道(
nvnadaulatsvyi )」と呼ばれています。このことは先に説明いたしました。
インディアンの価値観
何百といるインディアンの部族。彼らは、この大自然のなかで、あるときには交流し、また、あるときには戦闘をし、生き抜いてきました。その自然は、広大、同時に、場所によっては過酷なまでの気候を克服してこなければならなかったのです。中西部の平原を占めているPlainsと呼ばれる地域には、雨は少なく、また、冬の寒さは、マイナス40度にも達することがあります。この地は農作業をするには適さず、彼らは、狩猟を生活の糧としてきました。だから彼らにとっては、より発達した文明とは狩猟文化であり、それは農業文化よりも優れていると考えられてきたのです。自然の恵みである獲物は決して商業の対象ではなく、その年の収穫なのです。その収穫を必要以上に取れば、それは次の年に飢餓を招くことを知っていました。どんなに沢山のバッファローが草原に群れを成していても、彼らは自分の部族の人数以上のバッファローと射止めることはしなかったのです。一年に一人のインディアンが必要とするバッファローの数は、一頭でした。その一頭のバッファローは、毛皮から、内臓、そして、骨まで、ことごとく生活に必要なものと化して、消費されていたのです。彼らの狩猟の後には、ひとかけらの肉の残りもないし、また、腐った内臓すら残されていないのです。これが、自然と共存する最低限のルールであることを長い習慣のなかで引き継いできました。インディアン達は、大草原のなかを転々と移動しながら生活していましたが、一年のうち、いつになれば、どこにバッファローの群れが集まってくるのかを知っていたのです。谷を渡ってくる風は、バッファローが近くにきたことを知らせてくれたのです。全く、原始的な方法で仕掛けをつくり、地形を利用して、一度に何百等のバッファローを捕獲していました。そして、冬になると暖かい地方に移っていったのです。毎年、何百マイルという距離を移動しながら、夜は満点の星を眺めながら、そして、昼は、草花が色とりどりの花を咲かせる草原のなかで、自然と調和して、まことに平和な世界で生活していたのです。
伝説に見るインディアンの価値観
彼らが自然のなかで、動物達と共存共栄をしてきたなかで、どんな風に考えていたのかということは非常に興味があります。遊牧を糧としていた彼らには、文字が必要なかったので、言葉を通じて、沢山の伝説が伝えられています。そうした、彼らの生活の中での動物達に対すル考え方を、彼らの部族に伝わる伝説のなかからいくつか拾ってみました。かれらが如何に動物達を大切にしてきたかということが分かると思います。さあ、果たして、彼らのこのような動物との付き合い方は、あなたにはどんな風に映りますでしょうか・
インディアンにとって文明とは、
インディアンが決して農耕を営んでいなかったわけではありませんが、彼らの住んでいた場所は雨量もすくなく、決して肥沃な土地ばかりではありませんでした。そんなわけで、農耕で生計を立てることは不可能だったわけです。そのために彼らは狩猟民族として繁栄してきたのです。18世紀にヨーロッパから、天然痘が持ち込まれ、沢山のインディアンが術もなく死んでゆきました。そのときに農耕民族のオマハ族の人口は、1割に減ったといいます。集団で、一箇所に定住していた彼らの部族は、この流行病から逃れることができなかったのです。ミズーリ川の土手には、山のように詰まれて死体があったといわれています。一方、スー族、クロー族などの騎馬民族は、遊牧生活をしていましたので、病気が蔓延する前に住む場所を転々と変えて、この流行病から逃れたといわれています。こんなことがあったからでしょうか、彼らは農耕文化よりも狩猟文化のほうが進化していると考えていたそうです。
自然とともにいきる、動物とともに栄える、そんな彼らの考え方を伝説のなかに、覗いてみたいと思います。
熊狩りのこと
Lewis
and Clark Expeditionから
熊は、・・・我々が持っているものと同じような魂を持っている、そして、彼の魂は、われわれが眠っているときにわれわれの魂に呼びかけ、私がなにをするのか話をしている。
- ―― BEAR
WITH WHITE PAW
インディアンが、ホワイトベア(
グリズビー
)の狩猟に出かけるときには、・・・彼らは、自分の体に模様を塗り、通常、彼らが近くのほかの部族に戦争をしに行くときにするような、あらゆる神がかり的な祈りの儀式をする。
――Meriwether
Lewis
夕暮れになり、冒険隊のほとんどの隊員たちが、そこにいた、支配者のような、大きな茶色の熊[
グリズビー
]を引きずり出して攻撃するために、島に近づいた。が、その熊は、取囲んでいるわれわれのことを全く無視しているかのようであった。我々の隊がその場所で、容赦することなく脅しまくったが、それにもかかわらず。そして、指揮官が怪我をしてしまった。結局、我々はその晩は、そのまま何の痛手を加えることもできず、キャンプに戻ることになった。
―― Patrick
Gass
北の地方に住むインディアン達の間で、熊ほど尊敬の念をもって狩猟をされる動物はいない。すべての動物のなかで、熊は最も人間に近い生き物である ――Cheyenne(シャイアン)族とArapaho(アラパホ)族のような平原に住むインディアン達の多くの部族も、そうした考えを持っているからと思われるが、共食いになる行為のように考えて、熊の肉は食べない。 熊は、動物としての人間よりも賢い年上の兄弟と考えられていた。彼らは、植物に関する知識の精通者であり、治癒の名人であり、そして、巧みな神秘的芸術家でもあった。彼らは根を掘り、そして、洞穴やねぐらに住んでいたために、大地や地下に潜んでいる力とかかわりをもっていると考えられていた。そして、彼らのもつこうした力は死を超越したものであった。なぜなら、かれらは、冬が来るといつも死んだような状態になり、そして、春になるとまた、生き返ってくるからであった。
熊の物理的な体は、熊の狩猟者たちの真の標的ではなかった。狩猟者たちは熊の持っているとてつもない力を求めていた。そして、熊との戦いは、物理的なものよりもずっと、精神的なものであり、気持ちの問題であった。多くの部族の間では、熊を狩猟するもの達は、棍棒や槍といった手で扱う武器以外に鉄砲とか弓矢といったものを使おうとはしなかった。もし熊が、狩猟者たちが自分の命を与えるに相応しいと思わないようなときには、鉄砲はとにかく役に立たなかった。熊をしとめることは、部族間の戦いで敵を殺すことと等しいくらいに勇敢な行為であった。Cheyenne
( シャイアン
)族の男達は、狩猟した熊の数を数えていたし、また、Assiniboine族の戦士達は、かれらが闘いをして打ち破った敵の話のなかに、熊との戦いのことも含めていた。熊の爪で作ったネックレスは、熊をしとめた男の英雄的な行いと精神的な力の象徴でもあった。男達は、それを身に付ける資格を手に入れなければならなかった。
バッファローのこと
偉大なる創造の神が人々に、“これらの動物達は、みんなお前の兄弟なのだ。だから、この大地も彼らと共に使いなさい。そうすれば、彼らはあなた方の食料にもなってくれるし、また、着るものも差し出してくれるようになるのだ。彼らと一緒に住んで、彼らを守ってあげなさい。”
“特に、バッファローは、あなた方に食料も、そして、身を守る盾にもなってくれるのだから、大事にしなくてはいけない。バッファローの皮革は、寒さからも、暑さからも、いやいや、雨からだってあなた方を守ってくれるのです。あなた方がバッファローとともにいる限り、他に必要とするものはないでしょう。”
何回もの冬を過ごす間、人々は動物達と、そして、その大地で平和に暮していました。彼らがバッファローを殺したときには、偉大なる創造の神に感謝をし、バッファローの体のすべての部分を利用しました。そうして、なんでも必要なものができたのでした。
バッファローたちがこの世に始めてやってきた頃は、彼らは、まだ人間と仲良くやることはできませんでした。狩人たちが、自分たちの部落で使ういろいろなものを調達するために彼らを崖の上に誘い出しましたが、そのときには、彼らは自分たちを人間たちのために差し出すことにあまり気が進みませんでした。彼らは、自分たちが毛皮として使われたり、あるいは、冬を越すための食糧である乾燥肉になることを好まなかったのです。自分たちのひずめや角がいろいろな道具や家具用品にされるのが嫌であったばかりか、彼らの腱が、いろいろなものを縫い合わせる糸として使われるのを喜ばなかったのです。“だめ、だめ、”と彼らは言いました。“もう、私たちは君たちの罠には乗らないよ。もう君たちのごまかしにはだまされないさ。” というわけで、狩人たちが彼らを最後の崖ッ縁まで連れ出してくると、彼らはいつも、最後の最後になってそこで向きを変えてしまったのです。こんな風にして、協力関係が壊れてしまうと村人たちは飢えと寒さに襲われ、厳しい冬を越さなければならなかったのです。
ところで、村の狩人のなかに、自分の父親が素晴らしい弓の使い手であることをとても誇りに思っている娘のいる狩人がおりました。夏の盛りの間には父親の方はいつも彼女の所に毛皮のベストを持って来ました。一方、彼女の方は、そのお返しに鹿の皮をとても柔らかく、そして、真っ白になるまでなめして、それを外套にして父親に上げました。彼女の身に纏っている服は、まるで雪のようなガチョウの羽のようでした。そして、彼女が村の子供たちやお年寄りのためにつくったモカシンは、一番喜ばれる贈り物だったのです。
しかし、いまや、風に乗って舞ってくる雪の知らせと、折れた柳の木々の間に殆ど見ることのできなくなった鹿たち、こうしたことから、彼女は、バッファローの群れの一部が始めたこの拒絶は、本当にたいへんな問題になるということに気がついていたのです。そこで、狩人の娘は、そのことについて何かをしようと心に決めました。彼女は、その崖の麓のところに行き、上のほうを見上げました。そして、低く、優しい声で歌を歌いはじめました。“さあーっ、バッファローたちよ、私の所に下りてきて頂戴。もし、降りてくるなら、そして、私の結婚式の宴の時に親戚の人たちに沢山のご馳走を出してくれるなら、私は、あなたたちのなかで一番勇猛な戦士の花嫁となって、あなたたちの家族になるわ。”
そして、歌をやめ、耳を澄ましました。と、彼女は、ずっと離れたところで、かすかに雷の鳴り渡る響きが聞こえたような気がしました。
それから、彼女は、おもむろに、死んだ人を再びこの生の世界に呼び戻す魔法の力をもった生き返りの歌を唄い始めたのです。彼女は、彼女のお婆さんが教えてくれた歌を静かに唄ったのです。そして、ほんの僅かの小節を唄い終わると、その毛皮のしたにひとつのこぶができたのです。そこで、彼女とカササギが毛布の下を覗いてみると、なんとそこには、1人の男の体があるではありませんか。でも、まだその時には、その男は息をしていませんでした。彼は、只、冷たい石のようにそこに横たわっていただけです。そこで、なおも娘さんは唄を唄い続けました。そぉーっと優しく。と、なんと、さして時間が経たないうちに彼女の石が動き出したのです。彼は、生き生きと、しかも、とても強そうに立ち上がったのです。これを見て、バッファローたちは、驚いてしまいました。そして、彼らは狩人の娘さんに、“どうか、この歌を、どんな狩が終わったときでも、我々のために歌ってはくれないだろうか? そうすれば、私たちは、あなたの部族の人たちにバッファローダンスを教えてあげます。そして、そのダンスを狩に行く前に踊れば、あなたがたは必ず、沢山の獲物を手にすることができますよ。そして、あなたが私たちのためにこの歌を唄ってくれれば、私たちはみんなまた、元のように生きかえるんだから。”

3.
西洋人社会の価値観
アメリカにおける西洋人の歴史
日本人の多くは、アメリカは1つの国だと思っているのではないでしょうか。確かに、大統領の絶対的な権威を考えれば、この広大な国は、ひとつの国家であることにはまちがいないのですが、ただ、そこには様々な価値観、すなわち、日常での生活をするときの考え方にわれわれでは理解しがたいような論理が成りたっているのです。それを理解するには、まず、アメリカと言う国の歴史をウィキペディアの記述を参考にして、眺めてみることにしましょう。
ヨーロッパからの入植
アメリカに最初に西洋人が来たのは、16世紀になってからです。この時期、ヨーロッパ諸国は、航海術の進歩とともに、植民地の拡大にしのぎを削っている時でした。そして、1500〜1700年代にかけ、スペイン、フランス、イギリス等ヨーロッパの国々から多くの人が北アメリカにやってきました。この頃の開拓者たちは金・銀を探し求め、人々は次々に植民地を形成していきました。
1492年、コロンブスによりアメリカが発見されると、はじめに、アメリカに来たのはスペイン人です。彼等は、アメリカ南部とメキシコ北部に入り、この地を“New
Spain”と呼び、多くの人々がここに入植しました。そして、カトリック教が使節団をおくり、新しい都市を築きました。St.
Augustineはこうしてできた代表的な都市のひとつというわけです。
一方、北アメリカに移住をして来たのはフランス人達でした。彼らは、アメリカだけでなく、カナダにも入植し、Quebecは北アメリカにおける最初のフランス植民地となりました。フランス人たちは川や湖の水路ををうまく利用して毛皮製品の貿易を始めのです。彼らは更にミシシッピ川を下り、ここに新しい定住地を作りました。これが現在のMissouri州St.Louis、Mississippi州Natches、Louisiana州New
Orleansなどです。
これに対し、イギリス人がアメリカにやってきたのは1607年のことで、アメリカの東海岸VirginiaのJamestownに定住し始めました。イギリス人たちは先住民族(インディアン)と共存し、取引することを学びました。1620年にはイギリス国教会の分離派たち(Pilgrim
Fathers)がMayflower号に乗ってアメリカに到着し、MassachusettsのPlymouthに新しい定住地を作り上げていきました。彼らは英国国教会の伝統的な信仰や教えに反発し、宗教の自由を求めて新天地にやってきたのです。一方、イギリス国教会のあり方に不満を抱きながらもこれに所属し、そのあり方をプロテスタントらしいものへ変えていこうとする動きもありました。こうした人々が宗教の自由を求め、1630年になるとマサチューセッツのボストンに上陸しました。その数は1000人にも及び、彼らはPuritanと呼ばれ、Plymouthに入植していた人達と合併してMassachusetts
Bay Colonyを形成していきました。1634年にはボルチモア卿がメリーランドを創建し、ここに多くのカトリック教徒たちが移り住みました。
オランダのHenry
Hudsonがニューヨーク湾に入港したのは1609年のことでした。彼はこの土地を母国オランダのものと主張し、1624年になると次々にオランダ人が入植し始めました。1626年にはオランダ西インド会社がマンハッタン島をわずか24ドルという安い値段でインディアンから購入し、ニューアムステルダムを建設しましたが、そのわずか40年後にイギリスに奪取されることになります。そして、都市の名前が変わりニューヨークが誕生したのです。
アメリカには国家の祝日に、サンクスギビングディと言う日があります。これは、1600年代初頭、こうして、アメリカ大陸に移住してきた人々は、その年の冬は乗り切れたにしても、ヨーロッパと違う気候・風土のもとでは、十分の食料を確保することができず、寒さや食料難などで多くの人が命を失いました。そこで、入植してきた人々はアメリカの先住民であるネイティブ・アメリカンに、その土地の風土にあったトウモロコシの栽培の仕方などを教わったのです。こうして、その翌年には、冬を越せるだけの収穫を得ることができ、その豊作を祝い、そのお礼としてネイティブ・アメリカンを招待して、食事を振る舞ったのです。これが、今でも、「サンクス・ギビング・デイ」として、国民の祝日となっているのは、よく知られた話です。
イギリスからの独立
1700年代になるとイギリス人が次々に北アメリカに移住し、東海岸一帯に定着して13の植民地を建設しました。これらの植民地はそれぞれ独自の発展をとげ、北部(ニューイングランド植民地)では多くのピューリタンが定住し、自営農業と商工業を発展させました。一方、南部植民地では宗派も様々で、黒人奴隷を労働の糧として綿花・たばこなどのプランテーション(大農場経営)を発展させました。
フランスは西部に領土を広げ、多くの開拓者たちが西へ移動していきました。当時フランスとイギリスは折り合いが悪く、植民地をめぐってついに戦争が勃発しました。イギリスはフランスとアメリカ大陸の先住民族(インディアン)の両方と戦わなければならなかったことから、この戦争はフレンチ=インディアン戦争(1755-63)と呼ばれました。数年間に及ぶ戦争の結果ついにフランスが破れ、イギリスはMississippi川東側のフランス領土を全て獲得しました。
ところがこの戦争でイギリスは多くの負債を抱える結果となり、これらの負債にあてる資金調達のため1764年に砂糖法(Sugar
Act)を定めて砂糖に対して課税を行い、植民地住民の反感をかいました。また、貨幣法(Currency
Act)を定め、植民地の住民達が勝手に紙幣を印刷することを禁じ、本国の
貨幣を使うことを強制しました。植民地の住民達はこれらの条例に強く反発し、この結果、「代表なくして課税なし」"No
taxation without representation"という主張やイギリス製品のボイコット運動が広がり、印紙法はついに廃止されましたが、1773年には新しく茶法(Tea
Act)が制定され、植民地に対する茶の独占販売権が東インド会社に与えられました。これに反対する植民地住民がボストンに入港してきた東インド会社の船を襲撃し、茶を海中に投じました。これがボストン茶会事件(Boston
Tea Party)です。これによって植民地と本国との対立が一層激化したのです。
1774年には13植民地の代表がPhiladelphiaに集まり、第1回大陸会議(The
First Continental Congress)を開催しました。彼らは課税や他の本国からの弾圧について話し合い、植民地住民の基本権利を確認、本国に対してこれを主張しました。しかし本国政府はこれを無視したため両者の対立は更に激化し、1775年にMassachusettsのConcordで武力衝突が起こりました。この武力衝突を抑えるために本国からもイギリス軍がやってきました。植民地軍の小さな部隊がLexingtonでイギリス軍と衝突し、ついに独立戦争(1775-1783)が勃発しました。
この直後、George
Washington(1732-99)を司令官に選出して大陸軍(Continental
Army)が結成され、その後1776年7月4日に再びPhiladelphiaに集まった植民地代表者は、Thomas
Jefferson(1743-1826)らを起草者として独立宣言(Declaration
of Independence)を公布しました。
植民地側には独立に反対する大地主・商人もいて陣営も整わず、大陸軍の兵士たちは十分な食糧、衣料、武器もないまま厳しい冬を過ごさなければなりませんでした。しかし、独立宣言に補筆したBenjamin
Flanklin(1706-90)がヨーロッパ各地を訪問し、アメリカ独立の合理性を主張・運動に対する指示を訴えたことが功を遂し、イギリスの宿敵フランスは植民地側に応戦、スペインもフロリダの奪還を目指して参戦するなど、戦局は次第に植民地側に有利に展開していきました。
1781年10月19日にVirginiaのYorktownで大陸軍は決定的な勝利をおさめ、ついにイギリス軍は降伏しました。2年後の1783年に平和条約(パリ条約)が締結され、アメリカ合衆国が誕生したのです。
アメリカ合衆国のはじまり
大陸会議では連合規約(Articles
of Confederation)が準備され、新しい国家を納めるための最初の憲法として1781年に採択されました。この頃はまだ個々の州が強い権力を持っていたため連合会議という中央機関に力はなく、税制はおろか州間取引を調整する法律すら制定できませんでした。
イギリス13の植民地は合衆国設立後に州となりましたが、それぞれの足並みは全く揃っていませんでした。George
Washington、Alexander Hamilton、James
Madisonや他の政治家たちはこの憲法による政治に満足できず、1787年に憲法制定会議が開かれ、ここで初めて新しい憲法が制定されました。各州をとりまとめるには統率力のある強い政府が必要だったからです。
新しい憲法は、まず3つの政府機関を設け、三権分立を取り入れました。それが、Executive
Branch(行政機関)、Judical Branch(司法機関)、Legislative
Branch(立法機関)です。
Executive Branchは最高責任者としてここに大統領を置き、法の遵守を監督し、国民は4年毎に大統領を選出することになります。Legislative
Branchは新しい法律を作る最高機関で、Senate(上院)とHouse
of Representatives(下院)の2つから構成され、これを議会(Congress)と呼んでいます。Senateには、それぞれの州から議員を2人選出して送り込むことがでます。House
of RepresentativesはSenateよりも多くのメンバーから構成され、各州の人口に比例して代表者の数が決められます。人口の多い州は、人口の少ない州よりも代表者を多く選出することができるわけです。
Judical Branchは、最高裁判所(Supreme Court)と他の連邦裁判所から構成されます。
西部開拓の時代
独立後1800年代に入ると、アメリカ合衆国は次々と新しい領土を取得していきました。そのほとんどが諸外国から購入されたもので、多くの開拓者たちが新地を訪れました。
フランスはMississippi川の西側を所有し、ここをLouisiana
Territoryと呼んでいましたが、ヨーロッパ支配という野望のためにヨーロッパ大陸諸国への遠征を繰り返していた当時のフランス皇帝Napoleon
Bonaparte(1769-1821)が、軍資金調達のため1803年にここを合衆国に売り渡しました。アメリカ合衆国第3代大統領Thomas
Jefferson(在職期:1801-1809)は1,500万ドルという破格の値段(1エーカーあたり3セント)でこの領土を購入(Louisiana
Purchase)し、これにより合衆国の領土はほぼ倍に拡大しました。
Thomas Jeffersonは新しく拡大した領土を開拓するため、Meriwether
LewisとWilliam Clarkの2人を新地に送り込みました。彼らは、Mississippi川からMissouri川に入り、その上流を目指して西へと向かいました。この時彼らの案内役として重大な役目を果たしたのがSacagawea(サカガウィア)というインディアンの娘でした。一行は現在のNorth
DakotaやMontana、更には遠くOregonにまで足を伸ばし、開拓を進めていきました。1805年にはZebulon
PikeがLouisiana Territoryの西側を開拓するため、ロッキー山脈に向かってArkansas川を上流に進み、現在のColorado州まで足を伸ばしました。この時発見された巨大な山が現在のPike's
Peakです。
一方スペインは、現在のFlorida州にあたる広大な領土を所有していましたが、1819年に合衆国がこれを購入(Florida
Purchase)しました。これにより合衆国は大西洋側からロッキー山脈まで領土を拡大しましたが、テキサスは依然としてメキシコの一部でした。
北部と南部
独立を果たした後のアメリカ合衆国は、着実に領土を増やし順調に発展していきましたが、国内の北部と南部の対立関係が次第に表面化してきました。北部と南部では、政治的・経済的な相違点がたくさんありました。両者の経済・産業は、気候風土等の違いからそれぞれの特徴が現れています。南部よりも寒冷な気候の北部では、主な産業として漁業や貿易が発展していきました。農場主は家畜や羊毛をとるために羊を育て、多くの織物工場が次々と立ち上がりました。
一方南部は、暖かい気候から農業が発展し、たばこ、綿、米、砂糖等の作物が大量に栽培されていました。南部の農場は北部よりも規模が大きく、特に大きい農場はプランテーションと呼ばれ、労働力の要としてたくさんの奴隷たちを抱えていました。収穫した作物は北部や諸外国へと輸出されていました。商工業が南部よりも北部で大きな発展を遂げたのに対し、南部はそれらを北部や諸外国からの輸入に頼っていました。
時代はさかのぼり、植民地に最初の黒人が上陸したのは1619年のことでした。彼らは最初、北部でたばこ栽培を手伝っていましたが、多くの人が奴隷制に反対していました。初代大統領George
Washingtonも奴隷制度を否定しましたが、これを撤廃することはできませんでした。
1820年にはMaineとMissouriが新たな州として合衆国に加わる意志を表明しました。この頃になると奴隷制論争が盛んとなり、北部・南部対立の焦点となっていました。
1830年代、1840年代に入ってもこの奴隷論争は続きました。合衆国はその後1845年にテキサスを併合、この結果起こったアメリカ・メキシコ戦争で勝利を収めメキシコ領土を割譲、これが1848年にカリフォルニア州となりFree
Stateとして新たに合衆国に加わりました。
南北戦争
1860年にAbraham
Lincoln(1809-1865)が大統領に選出されると、まもなくしてSouth
Carolina州がアメリカ合衆国から脱退、Georgea州、Texas州などもこれに続き、1861年に軍人だったJefferson
Davis(1808-1889)を大統領とするアメリカ南部連合国(Confederate
States of America)を新たに立ち上げました。彼らは首都をVirginia州のRichmondに移し、Robert
E. Lee(1807-1870)を南軍の将軍に指名しました。
この頃、共和党全体で奴隷制度廃止の気運が高まり、共和党出身のLincolnが大統領に選出されたことで、綿花栽培が中心で奴隷制を推進したい南部連合国とのぶつかり合いがますます激しくなっていきました。1861年4月12日、Lee将軍率いる南軍がついに北部領土を攻撃し、ここに南北戦争が勃発しました。
連合国(南軍)と合衆国(北軍)の両者とも海軍を結成し、海上での戦いも幾度と無く繰り返されました。
最初はLee将軍率いる南軍が優勢でしたが、次第にUlysses
S.Grant(1882-1885)将軍が率いる北軍が攻勢に転じていきました。また、北から南に移動しながら戦いを続けていたWilliam
T.Sherman率いる北軍部隊も数々の勝利を収めました。
Lincolnは1863年に奴隷解放宣言(the
Emancipation Proclamation) を発布し、同年7月のゲティスバースの戦いで情勢は北部に好転しました。その後1865年に連合国の首都であるVirginia州Richmondが陥落して南軍は降伏し、1861年から4年間続いた南北戦争がようやく終結しました。
合衆国の歴史上ただ一度の内戦が終わって合衆国は再統一されることになり、連邦制が確立、奴隷制は1865年に廃止(合衆国憲法修正第13条)されましたが、黒人に対する厳しい社会的差別は残され、その後一世紀間に渡り、アメリカの社会問題として存続し続けることになります。
合衆国再統一
南北戦争終結後、合衆国憲法修正第14条により、かつて奴隷だった全ての黒人たちにも市民権が与えられ、彼らは自由民(Freedmen)と呼ばれるようになりました。戦後の南部は壊滅的でその傷跡は大きく、街や農地のほとんどが破壊され、人々は職もなく多くのものを失いました。
戦後の時代は再建の時代(Reconstruction)とも呼ばれ、連合国に加盟していた南部諸州が立ち直るまでに10年以上の歳月がかかりました。南部で新しい経済政策が始まり、奴隷制は違法とされました。プランテーションは解体され、BirminghamやAlabamaの様な主要都市で各種の産業が生まれました。特に製材や繊維産業がこの時期めざましい発展を遂げ、合衆国全体も急速に成長していきました。
この頃から多くの人々が西へと移住し始めました。特にカリフォルニアで金鉱が発見されるとその勢いに拍車がかかり(ゴールドラッシュ)、更に多くの人々が富を求めて西へと広がっていきました。1862年にはホームステッド法が出され、西へ移住する人々に土地が無償で与えられました。ゴールドラッシュやホームステッド法の効果で移民が増加し、農業が大規模に発展、機械化が普及して北部の有力な市場となっていったのです。人口の増加に伴って西部の領土は州となる条件が整い、1864年にNevada、1867年にNebraska、1876年にColoradoが次々に合衆国の州として誕生しました。
1862年にはUnion
Pacific Rail RoadとCentral Pacific Railroadの両者が、西と東を鉄道で結ぶ事業を合同でスタートさせました。西はCaliforniaから、東はIowaからスタートした線路は1869年にUtah州のPromontoryで最終的に結ばれ、ついに初の大陸横断道路が完成しました。この時、アメリカ全土の教会の鐘が鳴らされ人々は鉄道完成を祝いましたが、こうした鉄道完成に活躍した労働者は主に中国とアイルランドからの移民たちで、その後人種的にも宗教的にも少数派として苦渋を味わいました。
合衆国の急速な発展とともに、多くの先住民(インディアン=Native
American)が犠牲になりました。かつてトマス・ジェファソンが大統領だった時代(vol.5
西部開拓の時代)には友好的だった関係も次第に悪化し、西部への移民に土地を奪われ、1800年代の中頃にはミシシッピ川以西の一定地域に強制移住させられることになったのです。彼らに残された土地はほとんどなく、移民と先住民族の間で土地を巡る戦いが多発しました。戦いは合衆国軍隊との間にもしばしば起こり、軍隊が勝つと政府は先住民族に対して保護特別保留地(Reservations)を与えました。しかし、痩せた土地で先住民族たちは苦しい生活を強いられ、同じ保留地に違った部族が送り込まれることもありました。こうした保留地は、現在でも約300カ所残っています。
産業革命
1800年代後半になると世界中で産業革命が起こり、アメリカはそのリーダー的な存在となりました。この背景には、数多くの革新的な技術の発明がありました。
1876年にAlexander Graham Bell(1847-1922)が電話を発明しました。Thomas
Edison(1847-1931)が電球を発明したのは1879年のことでした。1892年にはDuryea兄弟がを初めてガソリン車の走行に成功し、Henry
Ford(1863-1947)とその仲間たちが自動車の製造工場をつくりました。このガソリン車が後の飛行機発明の大きなヒントとなり、1903年12月17日にNorth
Carolina州のKitty Hawkで、ライト兄弟(Wilbur
and Orville Wright)が距離にして120フィート(約37メートル)、12秒間の初飛行に成功しました。
産業革命と共にビジネスで大成功をおさめ、大富豪となったものもいました。Andrew
Carnegieは、最初に五大湖から鉄を運搬するための船をいくつも購入し、その後鉄道や炭鉱を買い、最大のスチール会社を築き上げ、業界では最重要人物と認められていました。John
D.Rockefellerは石油の分野でビジネスを興しました。ガソリンを精製し土地を貸与し、油田も掘りあてました。これらの石油を運搬するための鉄道やパイプラインも買い取って石油会社の先駆けとなり、巨額の富を得ることに成功しました。
大企業は多くの労働者を必要としました。彼らは時として長時間の労働を強いられたため、賃金引き上げ交渉やより良い職場環境を作るために労働組合を結成しました。この時に誕生したthe
American Federation of Laborは現在でも重要な役割を担っています。
新移民たち
1840年代から50年代にかけ、アイルランドとドイツから大勢の移民が押し寄せました。アイルランドの人々の場合、1845年のジャガイモ飢餓で300万人もの人が餓死する災難にあったことが背景にありました。大半が大都市に移住し、特に専門技術を必要としない職につきました。ドイツからの移民達は、新しいビジネスを興したり農業を営む者もいました。大都市に留まることに執着せず、多くは広い土地が入手できる中西部へ移住しました。
1850年代から60年代になると中国からの移民が増加し、多くはカリフォルニアに移住して鉄道工事や鉱山で働きました。この新しい移民の"第一波"は500万人以上におよび、早くに移住した"アメリカ人"との間の融合も必要でした。それぞれが異なる言語、宗教、文化を持ち込んだため様々な問題も起こりましたが、新生合衆国は彼らがより良い生活環境や仕事、土地を得ることができるよう機会を与えました。
1870年代には移民の"第二波"が押し寄せました。大半はヨーロッパからの移民たちで、その殆どがイギリス、オランダ、スウェーデン、ノルウェー等の国から仕事を求めて海を渡ってきた人たちでした。1890年代になると移民たちの傾向が変わり、今度はイタリア、ブルガリア、ポーランド、ギリシャ、ロシアからの移住者が増加し、その数は600万人以上にもなりました。
移民の数が急増すると同時に、彼らがアメリカ市民たちの職をおびやかしたり、貧困や犯罪を持ち込むのではないかという懸念がアメリカ市民の間に広がり、政府は移民の入国を管理する法律を制定することで移住を制限するようになりました。具体的には、英語を読み書きできない移民の入国を拒否する法律を議会が承認(1917年)し、更に移民の数を制限する法律(1924年)が施行されました。1929年には、年間に受け入れる移民数を上限150,000万人までとし、出身国の割合も定めました。当時は、全体の70%までの割合でイギリス、アイルランド、ドイツからの移民が認められました。一方、メキシコ、中央アメリカ又は南米出身者には制限はありませんでした。
こうしてみると、アメリカに入ってきた白人たちは、祖国ヨーロッパで成功することができなかった人達、そして、貧困がゆえに古い宗教を否定するような人達だったことが良く分かります。だからこそ、彼らは自分達の手で新しい国を作ったのです。その主体がスペインやフランスではなかったから、そこには、征服という言葉は出てきませんが、これはまさしくアメリカ大陸の征服です。しかも、南北戦争では、北軍が勝利を収めましたが、いまだに、南の人達は北軍に負けたとは思って居ません。それは、南部が自分達祖先が築いた国だからです。奴隷が解放されたとはいえ、北軍は奴隷のかわりに産業革命による機械化という新しい労働の形態をもたらしてくれました。一方、中西部では、新しく入植してきた人達は、インディアンと協約をした政府から、無償で土地を与えられました。その土地は、まさしく、草木も何も生えないような土地。それを鍬や鋤をつかい、馬や牛の代わりに人力で石を取り除き、開拓してきたわけです。かれらは、生活のために土地作りをしなければなりませんでした。が、依然としてインディアン達がそこを生活の基盤として存在していたのです。、土地の主導権をいつも命がけでインディアンと争って、守ってきたわけです。かれらこそ、この土地は、自分達の作り上げた畑であり、町であり、国であると思っているのです。その苦労は、何世代も前の話ではなく、ヨーロッパから渡ってきた曾おじいさん、曾お婆さんが指のつめをはがし、顔をしわくちゃにして汗を流した話なのです。ですから、ここの建国は独立戦争でもなければ、南北戦争でもなく、まさしく、わずか、100年前の話なのです。それが、ここに住む人達の人生観であり、誇りなのです。時代の流れでヨーロッパ人以外の人がどんどんこの地にも入ってくるようになりましたが、彼等は、自分達こそこの国を作った主役であり、この国の主権者だと考えています。
中西部には、それこそ、多種多様な祖国の持ち主がいます。今年の夏は、おじいちゃんの町に里帰りと言ってドイツに帰る人、そして、親戚があつまるアイルランドに帰る人、奥さんがオーストラリア出身のため、子供をつれてシドニーまでバカンスに出かける人、祖国はそれぞれでも、彼らの思いの共通点は、今、いるアメリカ、こここそ自分達の国であるということです。そして、この国を守るのは自分達だと真剣に考えていることです。
4.
多民族国家の価値観
この国ほど、まったく価値観の違う人達が独自の生活習慣で暮らしている国は、珍しいのではと思うのですが、これは、島国に住む日本人だけがそんなことを考えているのではないでしょうか。ヨーロッパのように、それぞれが独立しているのであれば、その国により価値観が違っていても何の不思議はないのでしょう。アメリカでもそれぞれの州が独立国と考えれば、その州によって価値観が変わっても何の不思議はないのです。州により交通規則は違いますし、消費税もモンタナではありません。その1つの州でさえ、面積が日本の国土よりも広い州が沢山あります。そんな州には、町の名前がノルウェーとか、スウェーデン、レバノン、さらには、アンゴラやスーダンなんていうところさえあります。当然、その人達の祖国なのでしょうが、かれらが全く同一の価値観で生活しているとは思えません。
もっと極端な例は、宗教の違いによる価値観の差です。ご存知のようにソールト・レイク・シティーはモルモン教の聖都です。この町に住む人のほとんどはもちろんモルモン教徒です。イリノイ州ノーブー市における迫害がひどかったため、当時の教会の大管長ブリガム・ヤングが聖徒達に西へ行くようにと指示しました。モルモン教徒に対する迫害は一層強まり、ノーブー神殿も燃やされました。この脱出を指導したブリガム・ヤングは、「西のモーセ」と呼ばれています。ネブラスカのプラット川に沿い、スウィートウォーター川を越えた聖徒が作った道はMormon
Trailと呼ばれるようになったのです。
彼らは、神について次のように考えているといわれています。
クリスチャンが「神」という言葉を用いるとき、それはこの万物を創造された、永遠の中に存在する唯一の神を意味します。しかしモルモン教の場合はそうではありません。彼らは多くの神が存在すると信じており、そのすべての神は以前は人間であったと考えているのです。つまり彼らが「父なる神」という言葉を使うとき、それは人間から進化した神が今この地上を支配しているという意味になるのです。モルモン教の創設者であるジョセフ・スミスはこう語っています。「全ての神々がそうしたように・・・あなたがたも神になれるよう良く学ぶ必要がある。」これが彼らの信じている教えなのです。
ここで私は、宗教論を論ずるつもりはありません。私が言いたいのは、広大な国土をもつアメリカには、こうした独自の考え、宗教を持って生きてゆこうとする人達が生活の場をもとめて自分達のユートピアを作ることができるのです。そこには、他の宗教、価値観の人達が入り込む余地はありません。
同じようなことは、アーミッシュの人達についても言えるのではないでしょうか。
Amish
Yahoo 百科事典から
16世紀のオランダ、スイスのアナバプティストの流れをくむプロテスタントの一派であるメノナイトから、1639年に分裂した一派。ヤコブ・アマンJacob
Ammanを指導者として始まったためアーミッシュとよばれる。イエスやアマンの時代の生活を実践しようとする復古主義を特徴とする。メノナイトと同様、ルターやツウィングリの国教会制度を拒否(教会と国家の分離を主張)、国民性やイデオロギーの違いで人を殺すより、牢獄へ行った方がよいとする平和主義を貫く。現代文明を拒否して電気や車を使わず、馬車を用いて、おもに農業を営む。地味な服装は信仰の表れである。アメリカ合衆国では、義務教育や兵役拒否で国家と争うが弾圧は受けなかった。権威や偶像を認めず、自然とともに暮らすアーミッシュの質素な生き方から何かを学ぼうとする現代人もいる。アーミッシュ単独の実数はつかみにくいが、メノナイト系全体では、1990年現在、北アメリカに約38万人、世界に約85万6000人といわれている。
そして、未だに健在なのは、日本人にもお馴染みのKKKやヒッピーたち。もちろん、古い町にいけば、イスラム教のモスクも町の真ん中に堂々とそびえています。そうです、この国の価値観は一言で言い表すことは到底不可能なのです。ですから、これがアメリカの価値観というのは、そのほんの一例を紹介しているに過ぎないといったほうが良いのかも知れません。
でも、われわれが一番奇怪に思うのは、アメリカ人の多くのひとは間違ったことをしても、あるいは、悪いことをしても、その罪は自分の代わりにキリストがその罪を背負ってくれると考えていることです。毎日曜日に教会に行き、懺悔するのはそのためのようにさえ思われるのです。どうしてそうなったのかは、分かりませんが、この考えがアメリカ人を楽天的にし、積極果敢に失敗も恐れず挑戦するという裏にあるような気がしているのは、私だけでしょうか。
民族による価値観の相違
祖国、つまり、曾おじいさん、曾おばあさんの育った国がドイツであり、アイルランドであり、イギリスであり、メキシコであり、イタリアであり、ポーランドであったりすることは、その子孫のしきたりや生活の風習は、それぞれの国のしきたりに従っているのは明白です。
ドイツ人は几帳面で、頑張り屋。勝手は、ギルドという組織があり、職人気質なところがあります。これに対して、イギリス人は、もともとが大英帝国の栄華を謳歌してきた国ですから、人の下で働くのはあまり上手ではないようですし、ノンビリ屋が多いように感じます。しかし、産業革命はイギリスから起こったことからも分かるように、長い歴史の中では、技術の革命の主役を担ってきたのです。フランス人は、実践よりも理屈が大好き。技術的な裏づけがなくても、自信たっぷりと言うのが彼らの特長。イタリア人やメキシコ人は陽気で、あまり細かいことに気を使わないという国民性を持っています。
アメリカ人といわれる人達は、こうした性格の人達の集まり、つまり、みんなが独自の性格、考え方、価値観で共存しているのです。お互いがお互いの存在を認めない限りは成り立たない国がアメリカといえるでしょう。否、認めるというより、お互いに干渉しないというのが正しいのかも知れません。ですから、暗黙の了解とか、常識的な事柄などというのは通用しません。すべてが文字で書かれた契約書がお互いの理解の根拠になるわけです。ここに、契約社会としてアメリカの必然性があるのでしょう。
価値観の裏にあるもの
アメリカに移住してきた西洋人たちは、それぞれの民族が、様々な宗教と、それぞれの歴史、それは、祖国の歴史であり、アメリカへの移住の歴史をもっています。かれらは、西洋文化の恩恵に浴した人種であるという、すなわち、西洋的な価値観の集団であるという共通点はあるものの、そこでは、それぞれの民族が、様々な宗教、生活習慣に基づいた価値観をもって、広大な大地のなかで生活を営んでいます。広大であるがゆえに、お互いが干渉することなく、この新天地を開拓してきた。その彼等の歴史を見ると、たとえば、独立後、バージニアでは、入植した白人達は、河口付近の静かな川とピートモンド高原に挟まれた肥沃な土地を、奴隷を使って耕作する農場を開拓することによって富をむさぼっていました。彼等はイギリスからの独立戦争と立憲君主の政府と言う考えからのし上がってきた者達でした。自分達自身を新しい形の国家に組み込もうという、とても手に負えない、統率のない集団であったのです。彼らには、彼らの社会が近代国家への変換の瀬戸際にいるというような自覚は微塵もありませんでした。入植の形はいろいろあるにしても、アメリカという大地で生活の基盤を築きあげてきた人達には、多かれ少なかれ、こうした、なりあがり者的な人生観をもった人達が、自分達こそ国家であるという意識のもとに、その考えを子孫に受けつないできたのです。従って、西洋人たちの間では、彼等は、自分達の存在意義を自分達の価値観を守ることにより主張して、お互いに共存しているわけです。。そこには、自分の価値観を捨てない代わりに、相手の価値観をも許容するという、共存の世界を思い描いてきたのです。
しかし、西洋人同士のなかでは、つまり、西洋文化を基盤にしている社会のなかでは、かれらは、このような形で共存を許容してきましたが、現地の先住民族に対してはそうではありませんでした。それは、先住民族側の歴史から見る限り、西洋人はアメリカ大陸の征服者であり、侵略者であるという事実は永遠に消し去ることはできないからです。私は、このことを一番良く知っていたのは、トーマス・ジェファーソンであり、かれこそ、西洋文化とインディアンの文化の融合に一番心を痛めていた白人ではないかと思うです。
宗教の力
われわれの価値観と言うものが、自分達の置かれた環境のなかでどのように生きてゆくか、そして、なにを子孫のために残せばよいのか、こんなことを考えるときに出来上がってくるものと思う。こうした考えが、日常の生活のなかで、習慣的な行動から外れるような環境におかれた場合に、われわれの思考を支配しているのではないかと思う。ただし、これは、日常生活における物的な対象物がそこにあるとき、つまり、物理的な満足感を追求するときの基準として価値観が存在している。一方、現実には、こうした、われわれの思考では及びもつかないもの、そして、物的な満足感は得られないにしても、精神的な満足感を与えてくれるものがある。これが、われわれの信心であり、宗教なのではなかろうか。決して、物理的な満足は得られないにしても、貧困に耐えられるのは、そこに精神的な満足感を与えてくれる何かがあるからでしょう。歴史を振り返れば、時の為政者は、治世の手段として宗教を利用したことが多々あります。。しかし、現在では、それは信仰という形で、誰もが平等に追求することのできる精神的な満足感であると言えるでしょう。
その宗教にしても、世の中には実に沢山のものが存在しており、アメリカは、その独立の歴史的な背景もあり、およそ、どんな宗教も受け入れられてきました。と言うより、古い宗教から、迫害を受けた新しい宗教が、新天地をもとめて、大陸のどこかに自らのユートピアを築きあげ、それを守りとおしてきたのです。社会的な現象ばかりでなく、自然現象も、そして、科学に対しても、それぞれの宗教は独自の解釈をすることさえあります。たとえば、アメリカの大多数の人は、宗教的な理由からダーウィンの進化論を信じていません。宗派の違うもの同士の結婚は、必ずしも幸せな結婚であるとはいえないのです。キリスト教も、イスラム教も、そして、多種多様な仏教も共存している社会、それがアメリカの社会なのです。だから、宗教の違う人同士の議論は、時として、心情的に宗教の違いとして妥協を許さないことがあります。日曜日には、教会に礼拝に行くことが当たり前のアメリカ人たちは、同じ教会に行く人達とは、お互いに信じあえても、別の教会に行く人達とは一線を画しています。ましてや、日曜日に教会にも行かず、午前中から買い物をしているアジア人は、信心の薄い、精神的に貧困な人と見ています。ですから、組織の中でもこういうアジア人の理論を真面目に聞こうとはしないのです。まさに、宗教の力とでもいうべき、こうした価値観がアメリカ人の生活の底に流れているのです。
5.
西洋人とインディアンの価値観の融和
先にも述べましたが、西洋人とアメリカ人との係わり合いを歴史的に考察してみれば、明らかに西洋人は、アメリカ大陸の侵略者であり、征服者なのです。東海岸では、イギリスからの入植者達は、ここに新天地を築くことを前提にアメリカ大陸に渡ってきました。しかし、南の地域にやってきたスペイン人は、金を求めて、武力でこの地を平定し、統治してきたのです。フランスは、商品としての毛皮が必要なだけでした。だから、ここの商標権だけを主張しているようなものだったのです。アメリカが独立したあと、西洋からの移民がどんどん増加し、東海岸だけでは受け入れが困難になると、西洋人の中西部への入植が始まりました。そして、やがて、この大陸には多大な鉱物資源があることがわかり、金が発見されると、白人の中西部への入植は一揆に増大していったのです。しかしながら、この広大な地には、何百という先住民族のアメリカ人が、農民として、あるいは、遊牧民として生活していたのです。そこで、この地をフランスから買収した新生アメリカは、この地の統治者がアメリカ合衆国であることをインディアンに説得する必要がありました。先住民族は、彼等なりの文化があり、価値観をもって、この地で何百年と生活をしてきたわけです。その彼等を説得するために、ルイジアナの買収を実現したトーマス・ジェファーソンは、インディアンと平和協定を結ぶことで、彼等の価値観を変えるという試みに挑戦したわけです。
かれがそのために演出したのは、わずか、50人足らずの学術調査隊を、このルイジアナ買収によって得た土地の調査と称して、送り出したことです。これが、有名な「ルイスとクラークの探検」です。
ルイスとクラークの探検
では、このルイスとクラークの探検とは、一体どんなものなのでしょうか。
アメリカは、1803年にフランスからルイジアナを買収しました。すなわち、当時、ルイジアナという地域、これは、アメリカ大陸のミシシッピー川から西の地域を漠然と示す言葉で、この地はフランスが毛皮の取引のために統治していました。一方、アメリカは、ヨーロッパからの移住が急激に増え、人口の増加にともないアパラチア山脈を越えての西洋人の入植をなんとしても進めなければならないという状況でした。独立戦争後、国の情勢は一段落していたとはいえ、新興国のアメリカにとっては、なんとしても国土拡大が必要だったというわけです。そこで、時の大統領トーマス・ジェファーソンは、フランスに通商の拠点ニューオーリンズの買収を打診したのです。これに対し、イギリスと対立していたフランスのナポレオンは、アメリカ大陸にイギリスに対抗することのできる大国ができれば、自国に有利になると考え、この提案に対し、ミシシッピー川から以西のルイジアナの売却を提案したのです。こうしてアメリカは、国土が一揆に二倍となるような広大な土地、210万平方キロをわずか、1500万ドルで手にしました。とはいえ、当時、この地方はフランスの統治下にあったものの、ここに住む原住民のインディアンは、必ずしも西洋の国の支配下にあったというようなものではありませんでした。そこで、ジェファーソンは、これらのインディアンに対し、この国の盟主はアメリカ合衆国であるということを知らしめる使節を派遣することにしたのです。ただ、当時の状況としては、この広大な土地を武力で平定することは到底不可能なことで、そこで、平和的にインディアン達に、アメリカの支配権を説得する手立てを考えたのです。そのための施策は、この地のインディアンの生活の実態を調査し、インディアン達に、アメリカ合衆国との友好的な条約を結ばせるというものでした。ただ、後者の意図を諸外国に気づかれると武力衝突になると考え、ジェファーソンはミズーリ川を遡り、太平洋側に流れる川との接点を見付けるための学術調査隊と言う形で使節団を結成したのです。しかも、その調査隊の隊長には、当時、まだ、30歳という、私設秘書の年若いメリウェザー・ルイスを指名しました。そして、そのルイスは、軍隊時代の上官であるウィリアム・クラークを副隊長として招聘するのです。ところが、なんとその条件は、この探検隊の中では、二人は全く同一の権限を保障するというものでした。当時、軍隊には二人の指揮官は置かないというのが不文律としてあったのですが、ルイスはあえてこれを破り、すべての命令には二人の合意がなければならないと約束したのでした。こうして、探検隊には二人の隊長が存在したわけですが、この二人の間には、探検の間、全く意見をことにするということがありませんでした。たとえ、意見が分かれても、どちらかに決めなければならないときには、その決定権は二人には平等に与えられるというもの。そこに二人の友情の深さを感じるわけです。
こうして、この探検隊は、1804年から1806年にかけての28ヶ月の間に、苦難を乗り越え、ミズーリ川を遡り、ロッキー山脈を越えてコロンビア川に合流、そして、やがて太平洋岸に到達したのです。この探検隊の魅力は、たった一人の犠牲者、しかも、それは病死という以外、全くの平和的なインディアンとの折衝の末にアメリカに帰還したのです。また、この旅には、インディアンの年若い女が通訳として同行し、彼女がこの探検隊のなかで幾多の障害を克服するときに大活躍をしました。その功績は、彼女の姿がアメリカのドル硬貨にモチーフとして描かれているほどのものなのです。
こうして、この探検隊がアメリカ合衆国の歴史の残した意味合いは、現在のアメリカ教育現場に携わる教師の人達をして、もし自分が歴史の史実のなかで、その現場に立ち会いたいとすれば、どんな歴史上の出来事かというアンケートで、一番、指示の高かったものが、アメリカの独立戦争でもなし、奴隷解放でもなし、また、アポロの月着陸でもなく、この「ルイスとクラークの探検」、そのものであると言わしめていることからも、その素晴らしさを感ずることができます。
ルイスとクラークの冒険が果たした役割
二年にわたる大冒険のあと、誰一人として犠牲者を出すことなくセントルイスに帰還したこの、「ルイスとクラークの探検隊」が、アメリカの歴史の中のヒーローとなったことは、言うまでもないことです。彼等は、この旅の行程のなかで、天体観測をし、これまでは未知の世界であったロッキーの山々を超えて太平洋へつながる広大な地図を完成しました。特にクラークは地図作りの名人で、その地図の正確さは今でも賞賛されています。ルイスは、この旅の途中、植物の採集と、動物の観察に余念がありませんでした。彼等は、それまでに知られていなかった178種類の植物と,
122類の動物の観察記録を残しています。しかし、大事なのは、彼らの本命である、インディアンについての情報と、彼等との平和的な協約の確立でした。
この調査隊は全行程をとおして、およそ50近くの部族と遭遇しました。これらの原住民アメリカ人の部族の人口、規模、習慣、しきたり、そして、生活の様式など、こうしたことを克明に記録に残してきました。彼等の生活のめまぐるしいほどの多様性は、彼らの日誌から非常に鮮明に想像できるのです。発見のための冒険隊が踏査した西部は“誰も住んでいない未開の荒野”でもなければ、ただ一つの“インディアンの世界”というわけでもなかったのです。インディアン達は自分達自身のことを、一つの完全に統一された集団ではなく、非常に沢山の種族からなり、――と考えていました。そこには、西洋人とは全く異なる価値観をもった人達がいたという事実がもたらされたのです。
この探検隊の後、西洋人は、インディアンのアメリカ人化の政策を打ち出し、それを実行しました。広大な土地を必要とし、その主権を主張する狩猟を生活の糧としていたインディアン達を、農耕文化に転換することにより、定住させ、ごくわずかの土地でも生計が確立できると言って、やせた居留地を設け、ここに彼等を強制的に移住させたのです。そして、アメリカ化ナイズをしたのです。悲劇はその後起こりました。それは、かれらが、定住するようになったところに西洋人が持ち込んだ天然痘が蔓延し、人口の9割を失った苦い経験を無視するものであり、そして、文字を持たないインディアンに英語を使うように教育し、名前までも、英語の名前を使うように強要したのです。こうしたことは、インディアンにしてみれば、彼等の独自の文化を喪失することであり、自らの価値観を否定することであり、自らの存在すらも否定することであったのです。今でも、多くのインディアンが、この西洋人アメリカのとった施策について、非難しているのです。
インディアンの立場から、
ここに、あるインディアンの子孫の言葉があります。これは、決して遠い昔の話なのではなく、お爺さん、お婆さんの話として話されたものです。
多くの原住民のアメリカ人の人々は今日、キリスト教を信じている。か、もしくは、古くからある信仰とキリスト教との混合的なものを見出してそれを信じている。また、他にもちぐはぐな記憶に頼っているものもいる。インディアンの子供たちを、文化の伝統を断ち切ろうと彼らの家族からの影響を取り除くために、政府が約束して作った寄宿学校に収容した。この学校は、非常に厳しい批判を沢山浴びました。“私のお婆さんは、13人に子供を生みました。が、生残ったのは、そのうちのたった4人だけでした。”とCayuse-Walla
WallaのKathleen
Gordonが、その悲しい気持ちに溢れた声でいっている。“彼らは、教区の学校に無理やりに行かされるまで、流暢に言語を話していました。・・・私のお母さんのお兄さんのPalphは、Salem[Oregon]の近くにあるChimawa
Indian学校につれていかれました。彼は、そこで、彼の生活様式を変えようと、強制的に自分の部族の言語で喋るのを禁止されたために、そこから逃げ出したのです。・・・3度ほど、逃げ出しては捕まえられ、捕まえられては逃げ出し、とうとう、最後に戻されたときには、彼にはパンと水しか与えられませんでした。そして、彼はそこで死んだのです。・・・私のお母さんの世代は、われわれの生活を懸念して、仕方なく英語を話すようになり、そして、我々のために我々の言葉を話すと罰せられるようになったのです。”
原住民の言語の喪失というのは、多くの年長の人達にとっては、悲嘆の根源のようなものです。Kathleen
Gordonが説明しています:“偉大なる創造の主が、我々が生命を授けられたときに我々に対する贈り物として彼から我々にくれたもの[が言語]なのです。彼が全ての鳥達に歌を、そして、それぞれに独特の歌を与えたように、全ての動物達にかれらにそれぞれ別の鳴き方を与えたように、我々もまた、もうすでに取り上げられてしまったけれど、自分達に独特の言葉をもっていたのです。”Nez
Perce族のAllen
Pinkhamにとって、言語の喪失とは、自己認識の喪失でもありました:“文明がわれわれのところに押し寄せてきたとき、・・・政府はこのように言っていた:‘全てのひとは、いまや英語の名前を持たなければならない;あなた方は文明開化されたのだ。’そうして、われわれNez
Perce族の人々の殆どが、最後には、自分の本当の名前ではなく、英語の名前をつけることになった。彼らがやろうとしたことは、われわれを新しいこの文明化された市民に作り上げるためにわれわれからわれわれ自身の自己認識を取り去ることであった。”
よく協定のなかで保証されている狩猟とか漁業の権利が、開発や法的な障害により、その実行が制限されるようになったものとして新たな対立の原因となっているのである。若い世代のChinookのTony
Johsonが言っている:“私のお爺さん、そして、そのほか、私よりも以前の人々は、勿論、魚を取っていた人たちであり、したがって、漁業権と言うものが私にとっても現実に非常に重要なのである。・・・漁業をして生計を確立しようと考えているChinooks族の人が非常に沢山いるのである・・・われわれは、魚、――チョウザメ、鮭、キュウリウオ、そして、ヌマガレイといったような魚を必要としているのだ。こうした魚達は、Chinooks族であるために必要な魚なのである。・・・われわれのインディアンとして魚を取る法的な資格は1980年代に取り上げられてしまった。・・・私の年代か、あるいは、それ以前の人たちは、どうやって刺し網で魚を取るか、そして、その網を修理する方法、あるいは、船を走らせる方法を学ぶことができた。しかし、最近の若い子供たち、私の息子の年代では、そのチャンスすらないのだ。”
インディアンの知識や若い人たちに対する価値を見てゆくことは、これまでに起きたことの後にもがいているようなものである。
“われわれは、同化という過程のために衝撃をうけたインディンアの三世代の人々について話をしているのである。”とJeff
Van Peltが言っている。 “われわれの教育のなかで、われわれが旧い法律に基づいて彼らを見つめなおし、検証しないのであれば、われわれは、われわれの先祖がいたその場所に辿りつくことができないであろう・・・しかし、われわれは、どうすればわれわれの子供たちに教え、そして、導いていく手助けをすることができるのであろうか? 汚染された水を例にしてそれができるだろうか? そこには、もういない鮭でそれができるだろうか? ワシだってもういないし、狼も姿を消した。熊もいないのに、それができるだろうか? 私が自分の子供に教えるために出かけようと思うところはどこにあるのだろうか? ”
Carolyn
Gilman
“ Lewis
and Clark Across the Divide “
現代アメリカ人にも、こうした歴史の事実にたいし、真正面から対峙使用と言う人がいます。次の文章から、われわれは何を反省すべきなのでしょうか。これは、詩人でもあるWilliam
Least Heat-Moon が、The
Journey of the Corps of Discovery ( Dayton Duncan , Ken Burns ) の本の中で述べている言葉です。
これは、なにも皮肉ではなくて、ただ、論理的に、私が気に入っているモンタナのBlackfeetによって作られた杉の木の鉛筆で、これらの言葉を書いただけである。その論理とは、つまり、Meriwether
Lewis, William Clark, Benjamin Rush そして
Thomas Jeffersonのあと、西部をアメリカが開拓しようという人道的な教養をもった人があまりにも少ないのではないかということである。Lewisに対して懸命に教育したようなJeffersonの壮大な望みは、悲しいかな、今日では全く空虚なものとなっているようだ。多くの国がその権力と正義を自分たちの周りの人々に対して拡大し、強めようとしていくその興味を考察すると、どんな知識をあなたは・・・することができるのかということを理解することが役立つのではないか。それは、その理解が、文明化し、訓練しようと努力をしている人々をして、かれらが効果的な作用を及ぼさなくてはならないと思っている人々の中にある概念と実際に対して彼らのやり方をうまく適用させることができるようにしてやることと同じようなものだ。Jeffersonとこの冒険隊がしたことは、期待どおりにすぐに、――あまりにもつよく“発展”の存在を信じ、価値があり、人道的な知恵によりわくわくさせられるようなものへの要求、そして先人の努力に対する国家の攻撃をことごとく打ち砕いた。
アメリカの先住民族の間での常識に、「vision
quest(洞察力の探求)」といわれるようなものがある。それは、通常、孤独と貧窮しかないような人里はなれた場所を、形式的に旅をするもので、そにに滞留することにより、その人は、調和をもたらし人生の目的を与えてくれるような、自分の存在というもの、そして、宇宙そのものについての新しく、明敏な知識を悟ることができるのである。私には、それはLewisとClarkがアメリカの代表としてある種の国家でもあった大ミズーリ川を遡っていったことが、正当な評価ではないかもしれないが、いま我々がアイデンティティと、目的と、調和と、そして、この豊かな大地の公正な分け前を求めているような、その後、何世代もの人たちが続けていく機会をもつた、Vision
questであるように思われる。われわれは、いまだ、その行くべきところからどれだけかけ離れた場所にいるのか、そして、どれだけたくさんの間違いをしたか、LewisとClark、そして私は、今、自分の手の中にあるそれを見ている。
Vision
Quest ( 霊感の探求)
William
Least Heat-Moon
6.
現代アメリカ人の価値観
「自由世界の盟主として、世界のどの国よりも強国でなければならない。」オバマ氏は大統領の就任演説でこのように述べていました。では、その自由とは一体どのようなものなのでしょうか。私なりには、それは、Of
the people, By the people, For the People。まさしく、これこそが自由世界ではないのかと思っています。そのためには、各個人はなにをすべきかということが、非常に大事なのではないでしょうか。そこにアメリカ人の価値観があるのでは思うのですが。つまり、わが身の自由は、周囲の人間の自由の保障でもあり、また、様々な価値感を持つ人達の自由の保障です。でも、その価値感が多様なわけですから、結局、すべてが自己責任で価値基準を持つということではないかと思います。
とは、いいながら、この自己責任の範囲は、それぞれの人の宗教観によっても違いますから、ますます持って、これを一口で言うのは難しいでしょう。そこで、われわれの価値感と何が違うかということを明らかにしながら、アメリカ人の価値感を覗いて見ることにします。
男女平等
アメリカには、様々な差別に対して、これをしてはならないとの法律があります。人種、性別、年齢、容姿、宗教、階級などにより差別をしてはならないというわけです。これはこれで、非常に素晴らしいことですが、実は、こういうことが問題になること自体、そこには、いまだ歴然として差別があるということだと思います。単一民俗国家といっても良いような日本の場合、人種や、宗教、階級などの差別がどんなものかを理解しにくいところがありますが、こうした差別に対しては、日本人であるわれわれも、これはなくしていかなくてはと言う気持ちです。しかし、いろいろな差別の禁止にしても、それを逆手にとって、逆に差別を主張しているようなこともありますからこれは理解に苦しみます。たとえば、男女平等についてですが、これは、別の言い方をすれば男女同権。確かに、アメリカでは、女性の地位は、非常に高く、能力のあるひとは、どんどん社会のなかで重要な位置を確保し、大活躍をしています。こうした男女平等になんら異論はありませんが、能力が欠けるのに、これを低く評価すると、それは男女の差別だとやられると、これは、いささか頭を抱えてしまいます。たとえば、現場の作業で、どうしても力仕事は男性のほうが都合のいい場合があります。また、危険な作業で、事故がおこる確率の高い作業、こうした仕事には女性は不向きだというと、これは、即、性別の差別と来るわけです。これは、まったくの私見ですが、仕事にしていも、日常の生活にしても、各人がそれぞれの役割分担をすることが、世の中の仕事を円滑に進めるためには必要なことだと思います。ですから、男女の差は歴然としているわけですから、これをお互いの長所を生かし、短所を補っていくような形は、決して差別ではないと思うのですが、・・・・。私自身、男女の区別をして、仕事を指示しているようにとられ、これをもって差別だと訴えられたことがあります。
確かに、営業とか、安全管理、さらには、品質管理などで、バリバリと能力を発揮し、組織のなかの責任者として、沢山の男性を部下に持って働いている女性はいます。その人達のなかには、自分の家族とも別れて一人で赴任している人もいます。これは、まさしく男女平等の姿として、実に心強いものを感じます。ただ、彼女達が与えられたジョブをそつなくこなしているのは、まさしく、ジョブ・ディスクリプションが明確になっていて、会社との契約のなかで仕事を遂行できていれば、遜色ないというアメリカ流サラリーマンの常識がその裏にあることは確かです。そのアメリカ流サラリーマンの常識を理解できないと、アメリカ社会での男女平等は、われわれ日本人が考えているものと随分異なるように思います。
つけ加えていうならば、年齢の差別もきわめて厳しい環境にあります。ある年配の従業員は、世の中の進歩に追随していくことができず、事務処理は間違いだらけ。これは、はっきりいって、その人の年齢からくる、一種の病気に起因するものなのですが、しかし、会社として、この年齢が原因して間違いを起こしているということを理由に、その人を解雇することは、年齢の差に基づく差別と解釈され、結局、解雇を打診することすらできないのです。ジョブディスクリプションには、どのような評価システムでその人のジョブが満足に遂行されているかどうか、そして、その評価に基づいて、サラリーが変わるということまで、詳述しないとこの問題は解決できないように思います。
宗教の自由
アメリカと言う国が、ヨーロッパから逃れてきたピューリタンであることはよく知られています。しかし、現在では、様々な宗教が存在しており、いろいろな宗派に分かれています。そこで、アメリカ人が宗教に対してどのような考えでいるのかについてみてみましょう。
これは、国士舘大学 政経学科 アメリカ人の宗教観からの引用ですが、もともと、プロテスタントは神と個の繋がりを尊重しています。つまり、個人が聖書を読み解いていく行為を通じての神と人との関わりが重要だという考え方です。神に対する責任、責務を一人一人が持つことで、神から自由を授かるという考え方です。このことは極めて重要なことです。すなわち、これによって「近代の扉」が開かれたのです。近代=個人主義、自由主義という概念へとつながっていったのです。
そして、アメリカにおける宗教の分布の実態に関する調査では、アメリカ人は、92%が神の存在を、そして85%が天国の存在を信じている。奇跡を信じるアメリカ人は82%であり、78%が天使の存在を、さらに74%が地獄を信じている。また、水没した全世界で、方舟の中のノアとその家族、動物たちだけが助かったという話を60%のアメリカ人が真実だと考え、世界が6日でつくられたのは本当だとする人は61%、そして、モーゼがイスラエル人をエジプトから逃す際、海を割ったのを実話だと信じる人は64%である。(杉田成彦氏のレポートから)
これが、アメリカ人たちの宗教の実際です。かれらは、日曜日に教会にいくことを生活のリズムのなかにしっかりと定着させております。教会に行くことにより精神的な満足感を味わっています。ですから、日曜日に教会に行かないひと達は、自分達とは全くことなる宗教を信じていると思っています。そして、そういう人達は、精神的に貧困な人達であり、自分達の社会になじめない人達とみているのです。国民の大多数が宗教に対する依存感を抱いていない日本人は、このことをどのように理解したらよいのでしょうか。アメリカ人の心のなかにある宗教に対する考えを理解しない限り、日本人はアメリカ人の価値感を理解できないのでは思っています。
日本人にキリスト教を信じなさいというのではなく、宗教というものの存在をもう一度問い直す必要があると言いたいのです。異文化の中で、共存しようと言うのであれば、われわれに宗教が必要なのか、必要なのは、何のためなのか、そして、神の前で、どのような姿でいなくてはならないか、など、日常生活のなかに宗教というものの意味を考える時間を作ってもらいたいということです。
個人主義
神の前では、万人が平等であると信じているかれらは、それゆえにきわめて個人というものを大事にします。自分の自由は、周りのひとが認めてくれるから成り立つものであり、したがって、自分が個人の主張をするのと同じように、他人の主張も認めなくてはならないと思って居るようです。ただ、問題なのは、それは、同じような宗教に基づく価値感を持った人達の中での話です。精神的に貧困と思われるような人に対しては、全く、相手にしていないということを知る必要があります。否、たとえ、その存在を認めていたにしても、いざというときには、なんら相手の存在を認めないということに注意が必要でしょう。
精神的なよりどころ
ヨーロッパの白人達の精神的なよりどころは宗教であるように思います。どんな宗教であるかは別にして神の存在を信じていることは、想像以上のものがあります。われわれには信じがたいことですが、彼らのうちの大半は、ダーウィンの進化論を否定しています。そして、すべての過ちは、その罪をキリストが自分に代わり背負ってくれていると信じています。つまり、それにより自分の過ちは償われると考えています。これは、時としてまことに都合のよいもので、キリスト教を心から信ずることにより、罪の償いはそれで済むと解釈さえしている人達が沢山いることです。ですから、彼等の宗教に対する従順さには感心する、と言うより驚くほどであります。これが彼らの生活の知恵であり、習慣であり、価値感なのであります。さて、日本人の罪の償いはどうなっているのでしょうか。
人生の目標
それぞれの人により状況は違うでしょうが、日本の場合、狭い国土で、一生、一生懸命働くと、やっとマイホームが手に入るというのが日本のサラリーマンの典型的な人生です。もちろん、最近ではその環境は随分変わってきているようですが。これに対して、人口密度の低いアメリカでは、家を手に入れるのが人生の目標なんていうことは、到底理解できないことです。では、彼等の人生の目標は、一体何なのでしょうか。一般的なサラリーマンの場合には、自分の家族を守ることではないでしょうか。家族との絆を大事にし、自分達の信頼できる友達と、平和で豊かな暮らしをすることではないかと思います。ですから、家族の位置づけは非常に高いものがあります。自分のサラリーは、成功報酬ではなく、契約で決められた仕事の遂行と、決められた拘束時間を守っていれば、それで、サラリーが保証されると思っているようです。ですから、勤務が四時に終われば、仕事が残っていても、また、会議の予定があったにしても、さっさと退社します。子供の学校に迎えに行く、買い物に行く、ボランティアで子供の野球、バスケット、サッカーに付き合う、挙句のはてには、二勤の勤務にいく、など、とにかく予定はびっしりと入っています。男女同権は、家庭内の仕事も分業です。アメリカでは女性もどんどん働きに出ていますし、サラリーも男女の差がありません。専業主婦でない限り、家族に対する献身的なサービスは家族同士の絆を築くには不可欠なのです。こんなわけで、とにかく、会社を離れれば、否、正確に言えば、勤務時間が過ぎれば、あとは、頭のなかは家族のことで一杯というのが、一般的なアメリカのサラリーマンの姿ではないでしょうか。
会社に対する帰属感は全くなし
日本人は実によく働きます。なぜでしょうか。それは、日本人には、「耐えがたきを耐え、忍び難きを忍び」では在りませんが、一つの企業に長く勤めることが美徳の象徴であるかのような考え方があります。長年勤務すれば、退職金も増えるし、また、会社の中での地位も、勤続年数によって上がっていく。これが、一昔前までの日本の企業の姿だったのではないでしょうか。最近になり、必要な人は派遣社員でまかない、仕事がなくなれば人員の整理をしてゆく。こんな姿が会社の経理状態をよくしているかのごとく、言う人たちがいます。しかし、その典型的なのが、アメリカの社会であり、そのアメリカの企業の実態がどうなっているかをよく観察してみる必要があるのではないでしょうか。
アメリカの雇用は、職務ごとに人材を調達するのが通例です。仕事の内容を公にして、その仕事に対してサラリーを提示する。雇われる側と会社がこれで合意すれば、契約を結び、社員として採用される。派遣社員ではないので、一度社員に採用すると、その仕事が完結しない限りなかなか解雇はできないが、しかし、その反面、こうして雇われたアメリカの社員の感覚は、全く日本の派遣社員と一緒です。その顕著な姿は、一口で言えば、会社に対する帰属感というものが全くないに等しいということ。
そもそも帰属感というのは、個人的には業績をあげ、昇進、昇格、そして、昇給をすることを目的に、会社に対して貢献しようという姿勢です。そして、長年の貢献により、その結果として、退職金がもらえる、社会的な地位はある程度は確保できるというもの。それが会社を通して実現するというわけです。しかし、派遣社員は違います。かれらは、仕事のプロです。会社の伝統やしがらみに惑わされることなく、そして、組織のなかの他部門とのコミュニケーションが悪くても、契約に書かれた仕事をそつなくこなして、それで契約した報酬を得れば、あとは会社に対しては何の借りもなければ貸しも残しません。仕事が終了すれば、さっさと会社を辞めて、次の仕事を探すというわけ。ボーナスもなければ退職金もない。そんな会社の将来の発展など、全く眼中にないといってよいのです。これがまさしく、ボーナスも決してないわけではないが、その額はすずめの涙ほど、そして、何十年勤務しても退職金が払われないアメリカ人サラリーマンの会社に対する態度です。彼らは、今いる会社で新しい知識や技能を身につけたら、あるいは、少しでも、それに携われば、自分はまるでその道の一流の技術者であるかのごとくのアピールをして、さらに高い給料を求めて転職するのです。一つの会社で長いこと居るというのは、こうした転職ができない、あるいは、向上心のないことの裏返し。大体が、高い給料を求めて転職しないような亭主は、家族の幸せを考えていないと女房から非難されるほどだから、かれらは、会社の発展などということには何の興味もなく、自分の次の職業をいつも探しながら、今の会社に来ているのです。
これに加えて、会社が外資系の会社であれば、ことはもっと深刻です。その会社の本社がアメリカにあるならともかく、アメリカのビジネスで設けた利益を、ことごとく自国に持ち帰ることを考えているような日本の企業をどのように見ているのでしょうか。
こんな話があります。ある購買担当者。アメリカの業者からものを買っているが、日本のトップは、いつも、馬鹿の1つ覚えのように、「コストダウン。コストダウン。」と、コストダウンの交渉を迫っている。でも、業者にコストダウンをさせても、儲かるのは日本の会社。会社が儲けたからといって自分の給料が上がるわけではない。それなら、業者のいう提示価格で買って、その会社が少しでも儲けたほうが、アメリカに税金が沢山入ることになる。だから、なにも、目の色を変えて、原料や部品のコストダウンなど、やる必要がない。アメリカの業者を大事にしたほうが、国のためになる。日本の企業の勤めるアメリカ人がこんな風に考えてもちっとも不思議ではないのです。
自分が努力して、日本の企業に儲けさせて、その利益は日本に持っていかれるなど、アメリカ人のすることではない。アメリカ人なら、アメリカの利益になることを考えるべきで、自分の会社が儲からなくても、自分と取引をするアメリカの会社が儲かれば、そのほうが理にかなっていると考えているのです。
帰属感のない社員になにができるか。
日本では、サラリーマンが副業を持つことを禁止しているし、自分がアルバイトをしているなどということは、あまり公にはできないことです。ところがアメリカでは、サラリーマンが昼間の仕事とは別に夜の仕事を持つことはざら。自分の回りのアメリカ人と比べ、あるいは、自分の実力からすればもっと給料が高くていいはずなのに、それと比べれば給料が低いと思っている彼らは、当然、手当てのつかない残業など、ばかげた話。むしろ、残業する連中は能力がないから、ぐらいにしか思っていません。彼らは、定時になればさっさと帰宅し、次の仕事場に急いで行きます。スーパーのカウンターで働くもの、病院の経理をするもの、もちろん製造会社の現場で働くものなど、その仕事は様々ですが、これは間違いなく豊かな生活を確保するための術なのです。それが高ずると、昼間の仕事で疲れると、夜の仕事がつらいから、昼間はできるだけ体力のいる仕事はしない、失敗してもその日のうちに取り返そうなんていう気はさらさらない、文句を言われる前にさっさと帰宅する、これが当たり前なのです。ひどいものになると、定時では夜の仕事の開始時間に間に合わない。そこで勤務時間がフレキシブルであるのをよいことに、自分の勤務時間をかえてしまいます。朝、一時間早く来て、定時の一時間前には帰ってしまう。会議があろうが、トラブルがあろうが全くお構いなし。そんなのが、一人や二人ではない、半分以上のアメリカ人がこんな感覚で会社に来ているのです。そういう彼らに、会社に対する帰属感などあるはずがありません。ましてや、業務改善や定期的なレポート提出など、彼らは全く「聞く耳持たず」の精神状態なのです。
アメリカ経済の破綻
アメリカのクレジット社会は非常に合理的にできていると思います。クレジットヒストリーで保証されない限り、クレジットで買い物をすることができません。従って、現金で買い物をするのは、自分に金銭的な信用のないことを表現しているようなもの。ですから、どうしても、まじめに働かないとクレジットが得られないというわけです。アメリカ人が必死になって働くのは、このクレジットをつかえるようにするためです。そのクレジット制度のもっとも重要な要素である信用と言う問題を、うまいからくりを使って金儲けをしようというわけで、どんどん住宅を販売し、そのクレジットの保証をするはずの銀行が、その保証に保険を掛けてアメリカの経済が膨張してきました。そして、その保険が空回りを始めたときにアメリカの大不況が起きたというわけです。これは、信用をたらいまわしにして、そのうち、どこに責任があるのか分からなくなってしたった結果ではないかと思います。そして、その保険を引き受けていたというのが、日本の銀行ということですから、全く、開いた口がふさがりません。結局、銀行が金詰りを起こし、保険会社が破綻をしたわけです。日本の銀行がアメリカの経済の破綻の一翼を担っていたというわけです。アメリカ人の価値感を知らずに、儲けることに聡い日本人がこのからくりの演技の一端を担っていたのですから、これは、日本人のビジネス感覚に何らかの警鐘を鳴らしているのではないでしょか。
アメリカは立ち直れるか
問題は、この仕組みのなかになんら生産性がないということです。マネーゲームのなかで、見せ掛けの信用と、その信用の裏づけを数字合わせでやっていたわけですから、この仕組みが破綻するのは当たり前です。それが、今の世界同時不況なのではと思っています。アメリカが、この不況から立ち直るには、アメリカがもう一度、技術に立脚した生産性の向上を図り、ものづくりにより財産を作っていくことだと思います。安い賃金と、大量発注だけで、生産拠点を東南アジアに移転し、一部の資産家だけが利益を上げているような社会では、まだまだ景気の立ち直りは遠いのではないでしょうか。
アメリカの自動車産業界では、これまでの大型車指向から、小型車、もしくは、環境対策車にまとを絞り、再生するということで、政府から沢山の補助金を引き出しました。しかしながら、その大半は、最高経営者の退職金に消えたと聞けば、これほど、庶民を馬鹿にした話はないでしょう。アメリカの車が売れなくなったのは、品質問題と指摘されていますが、これは、確かに日本車の性能の高さと、そのアフターサービスの充実振りから、これを説明する話として品質と言う問題を出してきたのではないでしょうか。しかし、アメリカ車が売れないのは、その価格にあります。部品のコストは、日本の部品メーカーからの調達も随分進んでいるはずですから、部品の購入費が高いというのは、必ずしも正解ではないでしょう。問題は、とにかく、人件費の高いことです。それに、退職後の福利厚生費、これが莫大な費用で、その結果、製造コストを押し上げているのです。会社の再生の条件として、環境対策車で、ある一定のシェアーが確保できれば、十分に採算性があり、会社の再生は可能であるといっていますが、日本人のサラリーの2倍も、3倍も人件費を掛けて、これで、競争力のある車ができるとは到底考えられません。アメリカの経営者は、このことを知りながら、見せ掛けの利益を出して、経営から逃げるというパターンをすでに頭に描いているのではと心配する次第です。
アメリカ経済の建て直しの機会はあるのか、ということですが、いまの経済の仕組みでは、かなり難しい問題ではないでしょうか。それでは、如何するかというと、保護貿易の形にする以外にはないでしょう。しかし、いまの世界は保護貿易は時代の流れに逆行しますので、結局は、何らかの法規制、とりわけ、欧州がやっているような、ISO9000とか、ISO14000に代わる仕組みを作ることではないでしょうか。具体的になにを如何するということはこれからの問題ですが、すでに、アメリカで日本の部品メーカーたたきが始まっています。その1つの例が、品質の全数選別という手段です。これは、GMとフォードが考えついたシステムで、納入した部品に不具合があると、納入製品の全量を選別するというものです。いま、アメリカでは、この選別会社が猛烈な勢いで成長しています。なんと、その会社の社員はもともとはGMとかフォードの品質管理部門の人達が独立した会社。というより、親会社が余剰人員を吸収するために分離した会社です。納入する部品は、PPM単位の品質不良の管理をしています。年間の納入部品の点数が、数万個でも、PPMで管理するなんていうばかげた話ですが、このシステムがどんどん浸透しつつあります。そして、部品に品質不良が見つかると、全量チェックが始まり、そして、チェックの終了時には、また、別の不良、不具合を見つけて、これを、カスタマーに報告し、また、別の不良の全量選別をするというわけです。もちろんその費用はすべて部品メーカー持ち。こんなことの繰り返しで、日本の部品メーカーはアメリカで利益を上げることが非常に厳しい状況にあるわけです。こういう仕組みは一時的には、アメリカの企業の生き残り策としては友好であるかも知れませんが、社会全体の生産性のことを考えれば、これは、明らかに生産効率を悪くしていることは確か。技術の進歩により社会・文化の発展に貢献するという、製造業の本来の姿がそこに見られないのは何とも情けないことのように思います。
7.
最後に
国際社会でのビジネスの基本は、異なる価値感の共存であり、ともに利益を上げることであると思います。様々な価値感が融和していくことが大事なことかも知れませんが、それは、1つアメリカだけを考えても、様々な民俗が存在し、その生活環境が異なることを考えると不可能であります。ですから、われわれは、人種差別の問題にしても、宗教の対立にしても、それが存在することを前提にしてビジネスをしてゆかなければならないと思います。ただ、お互いがお互いの存在を尊重し、共通の認識にたてるのは、アメリカでビジネスをする限り、アメリカであげた利益は、アメリカに再投資をし、アメリカを開拓してゆくという企業の基本的な理念がない限り、アメリカと言う国の中で、その企業の市民権を得る、つまり、アメリカ人にこの企業はアメリカ人が喜んで就職しようという気になれる会社にはなれないのではと思います。
アメリカには、まだ、南北アメリカの対立の問題、そして、永遠の課題として、インディアン居留地についての問題があります。これは、アメリカという国がもつ歴史的な宿命です。その苦悩と戦いながら、アメリカの発展のために、いまなお開拓精神を保ちつつ、アメリカのために尽くしているアメリカ人と、価値感の相違を乗り越えてビジネスを展開していく手立てを探っていくことが必要であると思います。
(
2009 07 20 )