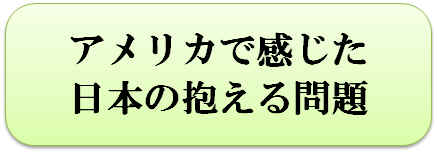
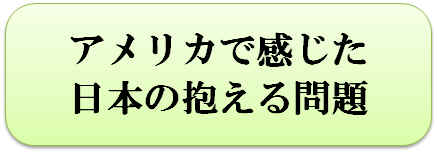
2009/08/28
日本の抱える問題
鈴木 誠二
日本は、国土が狭くまた、エネルギー資源の消費大国でありながら、化石燃料や鉱物資源に極めて乏しい国です。つまり無資源国なのです。
また、憲法でうたっているように、防衛についてさえも軍を持たないという無防衛の国。そして、最近の世相を見ると、詐欺や横領が蔓延し、軽犯罪が多発している、まさに無秩序の国といえるのではないでしょうか。
核家族化により、世代の間での文化の継承はおろそかにされ、精神的な充足感よりも物質的な満足感ばかりを求め、その結果、若者は働くことを嫌い、わが身の不都合は国の責任と言って、むやみやたらに権利を主張する。国の将来を憂う政治家は少なく、国民は生活の目的が定まらず、まさしく日本は、無能化の方向に進んでいるような気がします。これではグローバル化が進む世界の趨勢からどんどんおいてゆかれていくのではと懸念しているのは私だけではないと思います。
そんな日本の行く末を考え、これからの日本はもっともっと自立心を持たなくてはいけないと思っています。そのためには、なんと言っても、国民の一人ひとりが明確な目標をもつようにすることが大事ではないでしょうか。個人は人生の目標を、そして、国家は、日本の将来の目標をもつことです。そこに国民の生き甲斐が生まれてくるのです。新しい政府はそんなことを実現させてくれるようであってほしいと思います。
政治とは、まさしく、その字のとおり、国を治める政(まつりごと)です。そして、政とは、国民の社会生活を正しく取り仕切る仕事なのです。何が正しいか、そして、何が間違いであるかを取り決めたルールが法です。法は、国民に共通なルールなのです。幸いにして日本は単一民族、単一国家ですから、一億総国民の価値感はほとんど一緒です。ですから、法は誰もが納得する社会生活のための最低のルールとして受け入れられるはずです。世間には、その法に触れなければ何をしても良いというような風潮がはびこっています。自分の利益、欲望のためには、法の決めたルール、ぎりぎりのところで、否、軽い罪なら、それを犯してでも、自分の欲望を満たそうという人が沢山います。
しかしながら、法を守っていれば、それで世の中は豊かであるといえるでしょうか。安心できる社会でしょうか。決してそうではありません。法を守っていれば、それで十分に社会的な責任が果たされていると思ったら大間違いです。われわれは、法を守ることは当然として、その奥のもっと基本的なところに、道徳と言うものがあるのです。道徳は、人として恥ずかしくない生き方を教えてくれます。広辞苑によれば、「道徳」とは、次のように説明されています。
人の踏み行うべき道。ある社会で、その成員の社会に対する、あるいは、成員相互間の行為の善悪を判断する基準として一般に承認されている規範の総体
法律のような外面的強制力を伴うものではなく、個人の内面的な原理、今日では、自然や文化財や技術品など、事物に対する人間のあるべき態度もこれに含まれる
とあります。つまり、道徳は、私達の生き方の基本にあるもので、これを守らなくてはならないという強制力はないかもしれませんが、これを守らないことに対する社会的な制裁は、当然受けなければならないのです。それは、社会的な信用であったり、人間としての人格の喪失なのではないでしょうか。だから、われわれには、確たる道徳教育が必要なのです。今の教育システムのなかで、高等教育の費用を無料にするとか、あるいは、義務教育の教育費を国が負担するとかという議論も国民の人気取りのために必要なのかもしれませんが、そんな目先のばら撒き論争などではなく、それよりも、道徳教育を如何するかということを真剣に議論してほしいと思います。
道徳教育をしっかりやることは、民族の文化を正しく継承していくという上でも非常に大切なことです。核家族化し、家族というものの構成が何世代もが同居するという形が崩れ、親から子へ、そして、孫へという家族の中で実施されるべきしつけというものが消失し、いまや野放しになっている道徳教育こそ、国が何とかしなければ成らない、百年の計なのではないでしょうか。
家庭の中での親の権威の喪失も、そうした意味から非常に危機的な状態にあるのではないでしょうか。子供は、親よりも沢山の小遣いを持ち、それを、自分の欲望のために自由に使い、親の言うことも聞かないという社会がどうして、正常に成長し、発展していくのでしょうか。世の中の価値はすべて、金で決まるような考えを若者が持つとしたら、それは、国家の滅亡の前兆と言えます。
たとえば、親の権威と言うことでアメリカの例をとりますと、アメリカでは、子供が18歳になるまで、親の権威は絶対的なものがあります。子供は、それまでは、お金を自由に使うことができません。ちょっとした買い物も親の同意なしにはできないのです。これは、アメリカの、ものを買うときの支払いシステムによるものと思われます。つまり、アメリカでは、ものを買うときにはほとんどの場合はクレジットで支払い、現金を使うことはほとんどありません。もちろん、皆無ではありません。ただ、買い物をして、現金を出すと、これは、その人が、クレジットを作ることができないという、社会的な信用のないことを示すことであり、しっかりした職業についていないという現われなのです。ましてや、100ドル紙幣でも出して、支払いをしようとすれば、まず、「偽札」でないかどうかのチェックをされます。それが、子供であれば、これは犯罪が絡んでいると思われても仕方がないのです。ですから、子供が何かほしいものがあるとすれば、何とか親のご機嫌を伺い、親のクレジットで買ってもらうしか手がないのです。こんな状況ですから、子供は小さいときから、親のいうこと100パーセント従わざるを得ないのです。こうして、アメリカでは親の権威がしかと確立されているのだと思います。日本でも、何とか親の権威をもう一度、しっかりと確立してほしいものです。それが、日本の古来から伝わる文化を正しく継承し、守ることになるからです。
道徳教育と同様、懸念されるのは法治国家としての日本の秩序の問題です。今の世の中の風潮は、法に触れなければ、どんなことをしても良いというような傾向があります。ある政治家は、法に触れるようなことはしていないと嘯き、脱税まがいの会計、世間の常識では考えられないようなことを平気でしています。また、多少の法の侵害は、罪で償いがなされ、その償いが済めば、何の後ろめたさも感じない、そして、罪の意識すら忘れてしまうというようなことがしばしば見られます。
巷には、「オレオレ詐欺」という犯罪が後を絶ちません。町を歩いていると、若者による引ったくりなど、弱いものを狙った犯罪が溢れています。インターネットでは、毎日、数十もの、迷惑メールを受け取ったなどという経験はないでしょうか。情けないのは、墓荒らしをして貴重品を盗むもの、神社やお寺から、仏像や文化遺産の彫刻を盗むもの、こうした行為は、償いをして済むという問題ではないように思います。それは、人の心を傷つけるという、物的な問題よりもひどい、自分の欲望を満たすためには何をしても良いと考える、人間喪失の問題です。
私は、このような犯罪が後を絶たないのは、罪の意識の軽さにあると思います。法は、罪を犯した人に償いをさせることも大事ですが、それよりも、その犯罪を未然に防ぐということのほうがもっと、重要であります。かっては、犯罪の抑止力は、自分を取り巻く共存生活者に対する迷惑という考えが、犯罪の抑止力になっていましたが、今日では、家族の絆が薄くなり、家族ばかりでなく、親族や、近所の人達でさえ、個々の人の問題には無関心です。これでは、罪を未然に防ぐという抑止力はどこにも生まれてきません。ですから、最後に残る手段は個々の人間が抑止力を芽生えさせる以外にはないのです。そのためには、罪に伴う罰の重さを感じさせることです。
刑が、犯罪の抑止力になるかどうかの議論はなされていますが、その多くは、死刑が殺人を抑止するかという議論ばかりです。そして、その結論は、死刑があっても殺人は
亡くならない。したがって、刑は犯罪の抑止力にはならない。だから、重罰主義は必要ない。一口でいえば、現在の法曹界はそんな風に考えているようです。
ところで、現在の刑法がいつできたをご存知でしょうか。実は、明治40年に施行されたものが基本となっています。もちろん時代に即して、度重なる改正がなされてきましたが、その流れは、帝国時代にこれが悪用されたことに対する法曹界のこだわりがあり、時代に流されては良くないという反動から、とにかく、人権擁護、悪人にも人権があることを人道であるかのごとく解釈し、罪を如何に軽くするかということばかりが優先しているのではないでしょうか。裁判の弁護では、加害者はいつも決まって、
そんな意志はなかった
黙秘権をつかう
加害者にも人権はある。
被害者の死んだ人には人権はない
罪を犯しても、本人は反省している
そのときの精神状態は異常であった。
などということを平然と主張し、刑の軽減を求めるのである。これは、法を守ろうとまじめに生きている国民からすれば、まことにふざけた話で、まじめな国民は、罪を償わせることよりも、犯罪、そのものをなくしてほしいのである。つまり、刑は、償うための目安ではなく、罪を抑制するためのものであるべきなのだ。そのためには、罰をもっともっと重いものにする必要がある。少なくとも、社会的な情勢の変化に応じて、人をだますとか、老人や、女・子供などの弱い人を対象にした犯罪など、徹底してなくしてほしいと思う。犯罪が少なくなれば、警察も削減できるのである。
引ったくり、振込み詐欺、ねずみ講など、というのは、これは、他の人の人間性を否定するような発想であり、これは人間として恥ずべき行為であり、この抑止には罪を重くする以外にはない。このほかにも、墓荒らしやインターネットの迷惑メールなど、こうした、社会的規範に対する挑戦とも受け取れる犯罪に対しては、国家騒乱罪に匹敵するような刑が必要であり、徹底的な撲滅が法治国家には必要なのである。
ちなみに、アメリカでは、多額の支払いや送金にチェックを使っている。数千ドルというチェックを郵送していますが、これで事故は起こらないのです。われわれからすれば、よくもこれで事故が発生しないなと思われるくらい、国民は、このシステムを信頼しています。それは、アメリカの郵便システムが国の経済システムの基本の一部であるという認識がことごとく行き届いているからであろうと思います。これを盗めば、当然、現金強盗に匹敵する。かっては銀行強盗は、射殺されても仕方がないという時代がありました。その額の多少ではありません。郵便物を盗むということは、アメリカの郵便システムに対する侵害行為として、重大な罰則が用意されているからなのでしょう。こうした犯罪に対しては、その犯罪を防止する効力をもった刑が必要なのである。
アメリカの刑法が懲罰のためにあるのに対して、日本の刑法は、加害者の更正のためにあるといわれています。そんな形で加害者を守ろうなんていう時代はとっくの昔に変化していること、もはや、それは時代遅れであることに法曹界や霞ヶ関ははやく気付いてほしいものです。