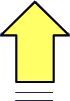
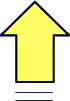
ooooo
投球動作を身につけるテクニカルポイント
【趣意説明】
ボール投げが得意な子と苦手な子を分ける境界線があるとすれば、それは「ボールを投げる経験の差」にほかならない。
ドッジボールや野球が好きな子は毎日繰り返しボールにふれ投げるうちに、自然と効率的な投球動作を身につけていく。雰囲気からして遠くに投げそうな子の動きを見ていると、出だしからすでに「決まっている」と感じることがある。効率的な投球動作を身につけることができれば、ボール投げがますます楽しくなる。
ここでいう効率的な投球動作とは上半身のひねりである。
●立ち方 基本の立ち方:「へそは横、顔は正面」(=ピッチャーのセットポジション)
| これから2通りの投げ方をします。遠くへ投げやすいのはどちらですか? |
白線(外)を引く。体育館で行う場合はラインを活用する。
A 両足をそろえて立つ B 片足を出して線をまたぐ(右投げの場合)
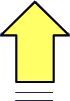 |
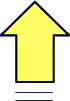 ooooo |
はじめに教師がやってみせる。その後、子どもにやらせてみる。
Bの方が腕がふりやすい、と体感できる。
個別評定のポイント⇒片足が線(ライン)をまたいでいるか
教師は子どもの真横に立ち、「へその向きが横向きになっている」ことをチェックする。
慣れてからも時々は「へそは横、顔は正面」と合言葉のように声かけするとよい。
●上半身のひねり方『バケツから遠くへポーン』
楽しい体育の授業2008年5月号に掲載された池田潤氏の修正追試。
修正点は「後方に置いてあるバケツの中のボールを拾って前へ投げる運動」にボールではなく紅白玉を使用する点である。


| バケツの中にある紅白玉をつかんだらすぐに投げなさい |
上の指示は練習中、紅白玉を一旦胸に抱えてから構えなおしてなげる姿が何度か目にはいったときに出したものである。
後方から前方への体重移動を経験させることで体のひねりがより鮮明にわかるため、流れるような動きを意識させる。
【よくある失敗例と対処法】
地面に置かれたバケツから紅白玉を手に取るには「しゃがむ」か「立ったまま体を傾ける」しかない。
「しゃがむ」のは先に説明したとおり、体重移動ができないため却下である。
そこで前もって指示を出す。
| 立ったまま紅白玉を取りなさい |
この指示で「立ったまま体を傾ける」ように動きが変化する。
そうすると、片足が上がりピッチングフォームに近い動きになってくる。
●ボールを持たない腕の使い方
体のひねりが十分できるようになった頃に、次の指示を出す。
| ボールを持っていない方の手を腰にあてて投げてみなさい |
右投げの場合、左手を腰にあてて投げる。あまり記録に変化が見られないこともあるが、子どもたちから「なんか投げにくい」と声があがるはずである。
ボールを持つ腕と持たない腕は、ちょうど天秤のようなもので、片方の反動がもう片方に直接影響を与えるものなのである。
つまり、ボールを持たない腕を強く体に引き付けることで、ボールを持つ腕のふりが格段によくなるわけである。
| 投げる直前に左腕(ボールを持たない腕)を前に突き出しなさい |
この態勢が常にできるようになれば、両腕を使うことの利点を理解するまであと一歩である。
| 投げる瞬間に左手(ボールを持たない手)を胸にぶつけなさい |
教師がやってみせるのが一番いい。
握りこぶしをあてるようにするくらいがちょうどよい。