血液型の推移シミュレション
(1)はじめに
ABO式の血液型は、赤血球の膜の表面に結合している糖鎖の先端が、個々人が持っている
転移酵素の種類によって、構造が変わっていることから区別しています。
具体的には、アセチルグルコサミンが結合しているとA型、ガラクトースが結合していると
B型、両方結合しているとAB型になり、両方ともないとO型となります。
ですからO型はゼロ型といったほうがいいのかもしれません。
日本人の血液型はABO方式では、
A型 39%、B型 22%、O型 29%、AB型 10%
とのことです。
この割合は、1000年後にはどうなるのでしょうか。特にAB型は少ないので、やがてはなく
なってしまうのでしょうか。
(2)遺伝される血液型
ABO式血液型に関する遺伝子はA、B、Oの3種類ありますが、関係する染色体は2個しか
持てません。したがってすべての組合せは
$\qquad $ AA、AB、AO、BB、BO、OO
の6通りとなります。
通常A型と表現されるのは、遺伝子型ではAA型とAO型、B型はBB型とBO型があります。
そこで、O型はOOと表記します。
日本人の遺伝子型の割合はネットでいくつか調べたところ、およそ
$\qquad $ AA型 8%、AO型 31%、BB型 3%、BO型 19%、OO型 29%、AB型 10%
でした。ただし、いずれも出典は明らかではありませんでしたので、おおまかな値としました。
(3)遺伝される子の血液型
まず、両親の各遺伝子型によって、子の遺伝子型はどうのような可能性があるか調べます。
(i) AA×AA 100% AA型
(ii) BB×BB 100% BB型
(iii) OO×OO 100% OO型
(iv) AA×AO、AO×AA
$\qquad $
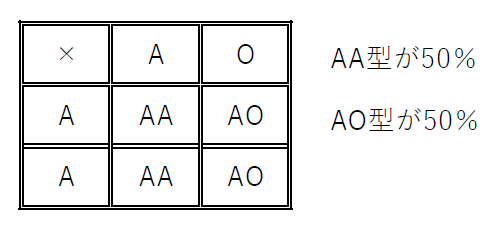
(v) AA×BB、 BB×AA
$\qquad $
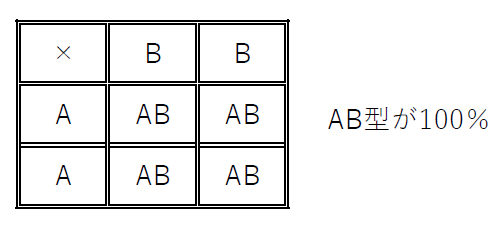
(vi) AA×BO、 BO×AA
$\qquad $
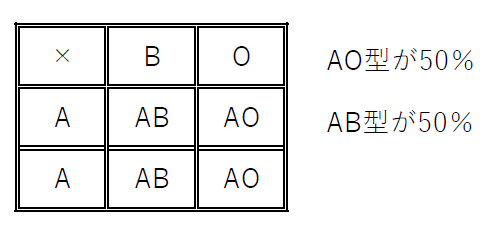
(vii) AA×OO、 OO×AA
$\qquad $
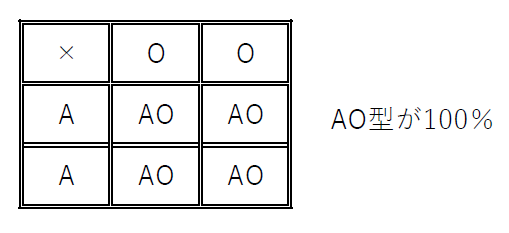
(viii) AA×AB、 AB×AA
$\qquad $
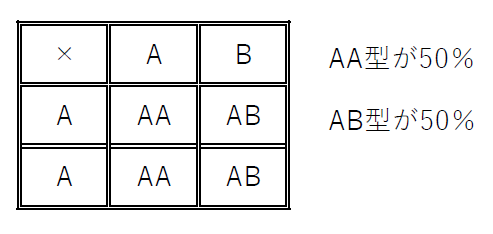
(ix) AO×AO
$\qquad $
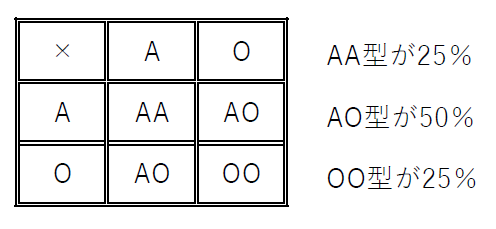
(x) AO×BB、 BB×AO
$\qquad $
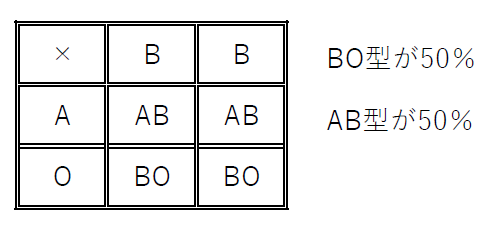
(xi) AO×BO、 BO×AO
$\qquad $
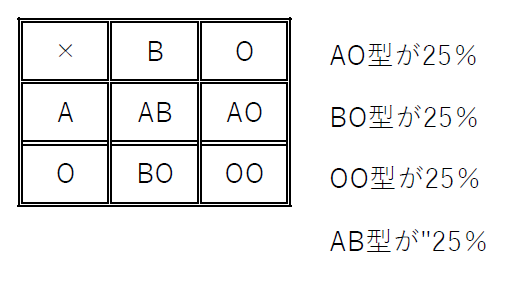
(xii) AO×OO、 OO×AO
$\qquad $
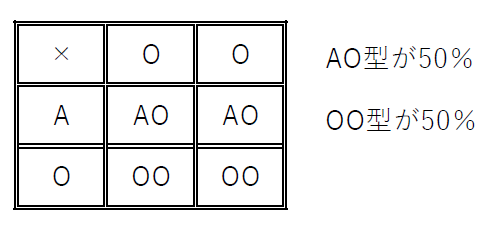
(xiii) AO×AB、 AB×AO
$\qquad $
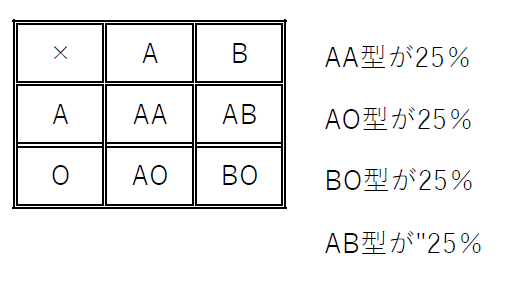
(xiv) BB×BO、 BO×BB
$\qquad $
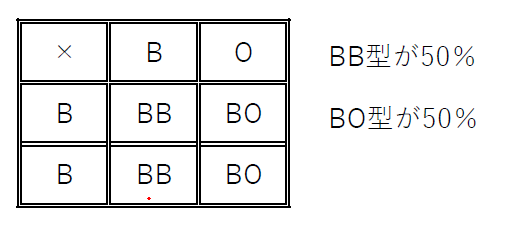
(xv) BB×OO、 OO×BB
$\qquad $
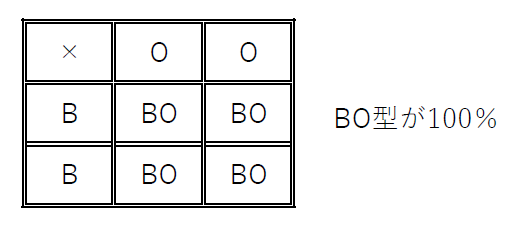
(xvi) BB×AB、 AB×BB
$\qquad $
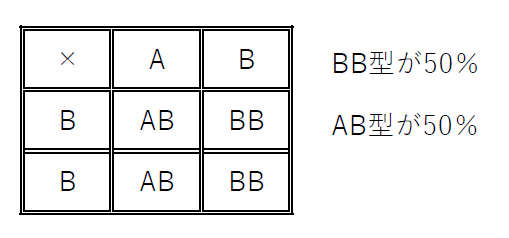
(xvii) BO×BO
$\qquad $
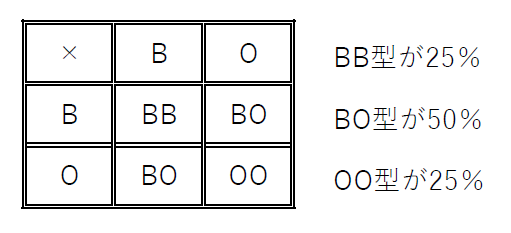
(xviii) BO×OO、 OO×BO
$\qquad $
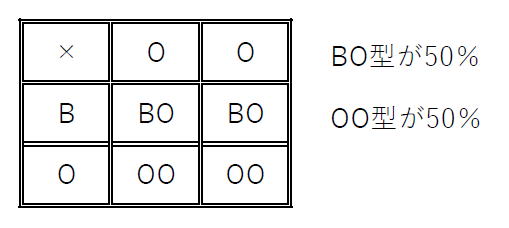
(xix) BO×AB、 AB×BO
$\qquad $
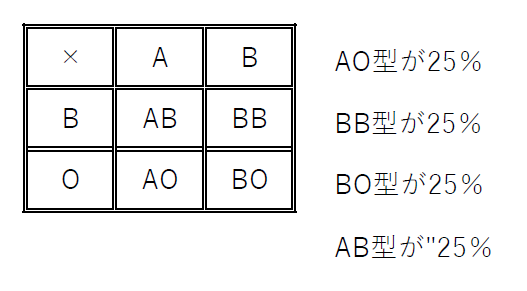
(xx) OO×AB、 AB×OO
$\qquad $
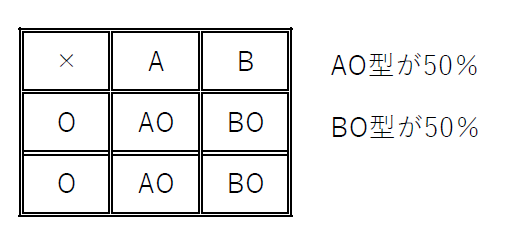
(xxi) AB×AB
$\qquad $
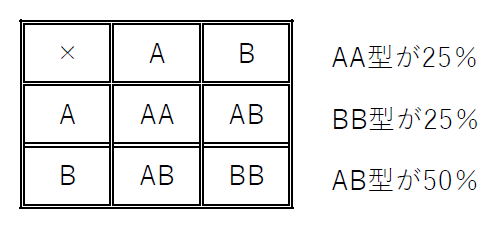
(4)仮定
シミュレーションするにあたって、次のような仮定をおきます。
(1)血液型に男女の差はない。つまり、同じ母集団分布に従う。(これは正しいようです)
(2)両親の遺伝子型によって遺伝される子の遺伝子型は、どれが選ばれるのも同様に確からしい
(同じ確率で選ばれる)とする。
(3)稀にある特異なケースは考慮しない。(必要がない)
(4)世間でいうところの、血液型による相性は考えない。すなわち父親、母親は任意抽出される。
(5)方法
ソフトはExcel VBAを用いました。
一様乱数を3個用い、1つ目と2つ目で、父親と母親の遺伝子型を決めます。
例えばこれがAA型とAO型だった場合、子どもの遺伝子型は、3つめの乱数 wが
w<0.5 ならば AA型とし、w>=0.5 ならばAO型とします。
これを10万回繰り返して集計し、各遺伝子型の比率を求め、第2世代の分布とします。
次に、得られた第2世代の分布をもとに、再び10万回計算し、第3世代の分布を求めます。
これを100世代繰り返して、得られたデータをグラフにしました。
なお、計算は20秒もかかりません。さすがExcelです。
$\hspace{5em}$
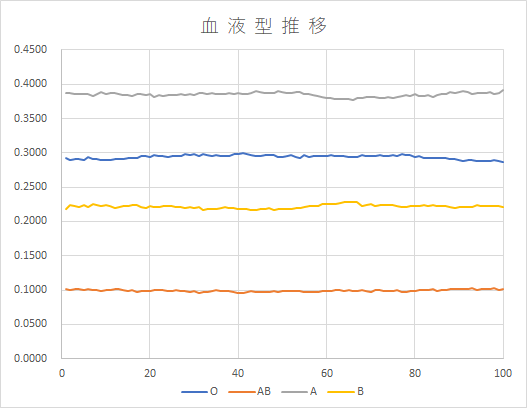
これからわかることは、
100世代、およそ3000年経っても血液型の比率は大きく変化しない
ことです。何となく安心しました。
というより、大きな集団における遺伝子の割合は安定しており、これを
『ハーディ・ワインベルクの法則』といいます。
この法則が破れるのは、
(1) 外部からの要因として、民族の大移動
(2) 内部の要因として、特定の血液型を持った人が新種のウイルスにより死亡
(3) 何らかの原因による優性的突然変異
などが考えられますが、SF小説ではありませんので心配する必要はないですね。
メインメニュー に戻る