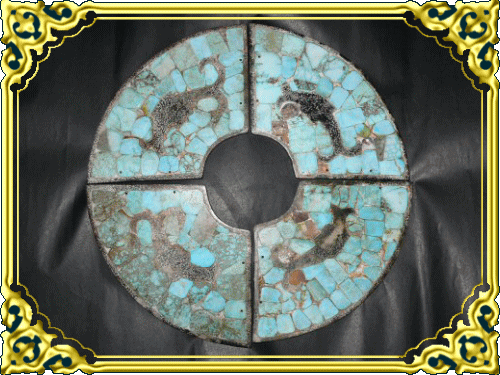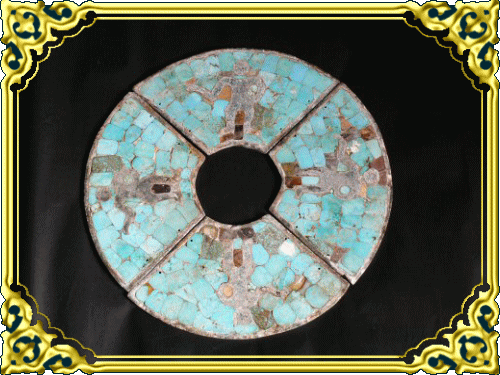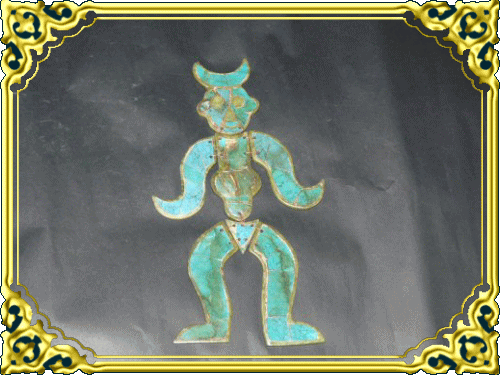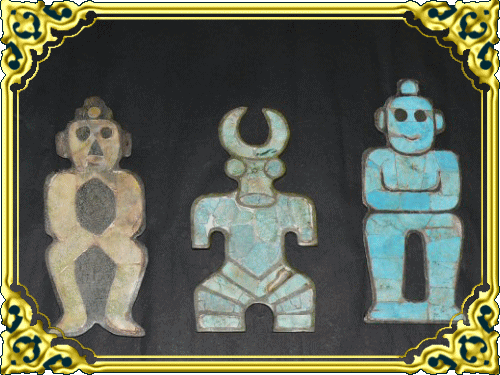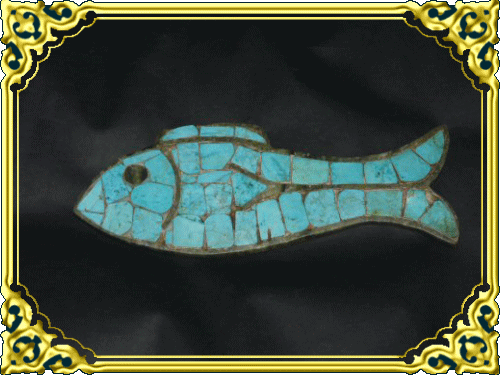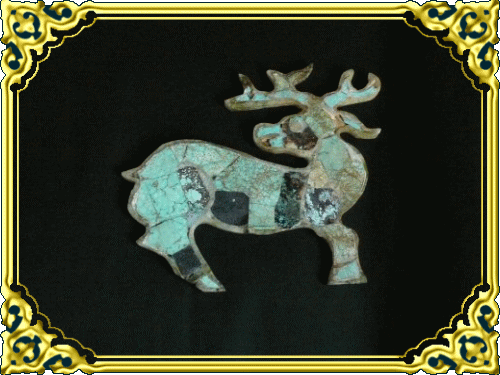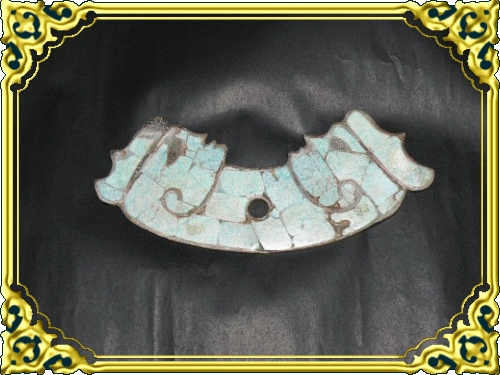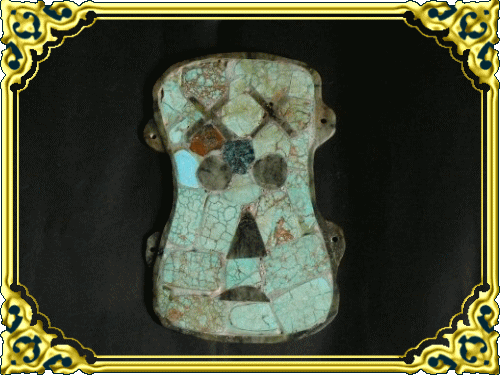斉家文化で高度な象嵌技術の玉器が完成していた 佐倉市 本間崇義 私は中国で、斉家文化のトルコ石象嵌の玉器を沢山集めた。私の集めた象嵌のある玉器は、斉家文化のものだと確信しているのだが、中国の考古学論文では、象嵌のある玉器の出土例が殆ど無い。考古学の論文で見る限り、斉家文化にはトルコ石象嵌の玉器は無いことになっている。 しかし中国アモイの上古文化芸術館には、象嵌のある玉器が、斉家文化のものとして展示されている。 そこの展示パネルには、斉家文化で高度な象嵌技術が発達したとの説明もある。 このアモイ上古文化芸術館の展示品を見れば、斉家文化にトルコ石象嵌の玉器はあると証明できる。また私の収集品は斉家文化のものとだと証明できる。 注:斉家文化に象嵌の無い玉器の出土例は沢山ある。また近隣の文化で玉器が出土するのは斉家文化だけです。だから象嵌のある玉器もまた斉家文化のものであると推定できる。 アモイの上古文化芸術館の展示品を見る前に、私が集めたトルコ石象嵌の玉器の象嵌の技術の素晴らしさを見て頂きたい。下の鹿の玉器は高さ41㎝もある。平らな玉(ぎょく)を加工し、トルコ石を嵌めこむ溝を堀り、そこにトルコ石等を隙間なく嵌め込んである。目立たないが縁の部分と底面が玉(ぎょく)である。 象嵌されているのはトルコ石の他にあまり硬くない綺麗な石も使われている。 接着剤には漆を使ったのかもしれない。3700年の時を経ても一片の剥離も無い。鹿の玉器は五つのパーツからできていて、パーツを結ぶ紐を通す穴が明けられている。この細い穴も金属工具が無い時代に古代人が明けたものである。玉を嵌めこんだのち研磨もしてある。造形の芸術性も素晴らしい。あまりにも素晴らしいので額に入れた飾ってある。  下は玉器ではなく、斉家文化のトルコ石象嵌の青銅器であるが、角、ひずめ、耳、尻尾 などの表現が上の玉器にソックリである。下の青銅器は上の玉器よりずっと小さい。 やはり青銅の原料は玉より高価であったらしい。青銅器の出土例も少ない。 下もトルコ石の象嵌のある玉器だが、黒い部分が玉(ぎょく)である。黒い玉の枠の中に トルコ石の小さな切片が隙間なく嵌めこまれている。そのトルコ石は嵌めこまれたのちに 研磨され、今に至るまで一片の剥落無い。右のものは首飾にするための紐通しの穴がある。 下は仮面の様に見えるが左右二つのパーツに分かれている人の顔。 高さ21.5cm、幅23.6cm、厚さ5mmもある アモイの上古文化芸術館の展示にも左右二つに分かれた人の顔の玉器が展示されている。 二つのパーツを結び付けるための紐通しの細い穴が左右にある。 細い穴を開ける技術が斉家文化にはあった。  トルコ石象嵌の玉斧。左のものの象嵌はトルコ石らしいが、右のものの象嵌は トルコ石ではないらしい。  右のものも左のものも 同じものである。この玉は半透明の玉で、後ろからライトを当てると 半透明でひかり場透けて見える。このものの上部には紐通しの細い穴が二つあるので、 首にかけて用いる装飾品であったかもしれない。
下の写真の様に、中央に円形の穴があり、玉で出来た円盤を”玉璧”という。この”璧”の形は長江下流の“良渚文化”で生まれ、黄河上流の斉家文化に伝わった。。また“玉琮(ぎょくそう)”も“良渚文化”で生まれ斉家文化に伝わっている。象嵌の無い玉璧、玉琮は斉家文化で出土している。 ちなみに完璧という言葉は故事から造られた言葉であり、壁にちなむ故事である。 故事に出てくる壁には象嵌は無かったと思われる。 壁の故事については”和氏の壁”で検索されたし。
下の写真のような円筒と立方体を組み合わせた形を琮(そう)という。琮(そうもまた長江下流の良渚文化から黄河上流の斉家文化に伝わった。長江下流と黄河上流では相当な距離がある。その距離を超えて、斉家文化に伝わった。 良渚文化の琮はかなり大型で細い線で紋様が刻印されていた。斉家文化に琮が伝わった時には琮の形は小型化され簡素化されて刻印も無くなったが、象嵌が加わった。
斉家文化の玉器の分類の中に、玉神器という分類があって、それによれば、その大部分は玉の全身像とか、トルコ石で象嵌された玉の人物像である。男女の別があり裸体であると書かれている。頭に髷のようなものを結ってるが、髷の結い方で男女が分かるようである。何故これらが玉神器と言われるのか、何故裸体の人物像なのか分からない。
斉家文化には玉器もあるが青銅器もある。右の一個が青銅器  斉家文化には動物紋様の象嵌のある玉器も沢山ある
ここからは人面紋の玉の牌飾。夏王朝の遺跡から出土した銅牌飾とソックで、 夏王朝の銅牌飾のルーツが斉家文化にあることを示している
斉家文化の人面紋の玉器と青銅器。上が玉器、下が青銅器  ここからはアモイの上古文化芸術館の展示品について 中国の考古学論文には、象嵌のある玉器の出土例が殆ど無い。ところがアモイの上古文化芸術館には象嵌のある玉器が展示されている。パネルには斉家文化で高度な象嵌技術が発達していたとの説明もがある。下は青銅器の象嵌品1個と玉器の象嵌品4個の展示。  上の展示の背景には高度な斉家文化の象眼技術についての説明が書かれている。これを見れば斉家文化で高度な象嵌技術が完成していたことが分かる。その説明パネルの拡大写真が下で、上古玉文化探究之三:齐家文化 (←クリック)のページから。 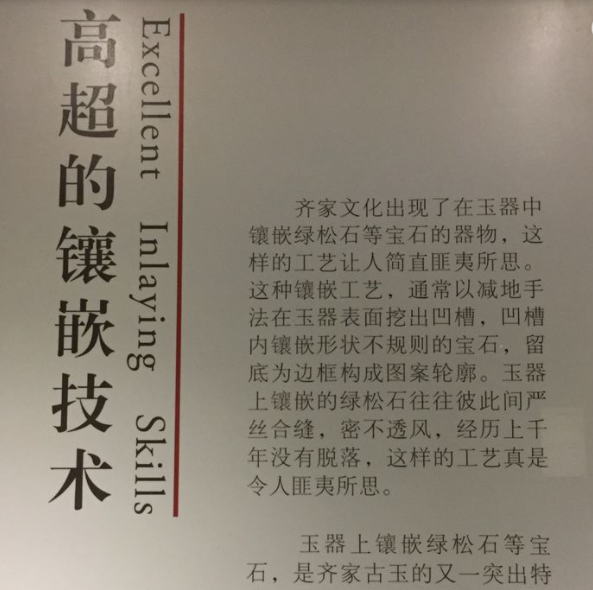 その説には、斉家文化に玉器に現れた象嵌のトルコ石や宝石の工芸には人は驚かざるを得ない。通常玉器の表面に溝を作りそこに不規則な宝石をはめ込み、その輪郭で紋様を構成している。玉器に嵌め込まれたトルコ石は隙間のない縫い目のようなり、密着していて、数千年たっても脱落が無い。このような工芸には驚くばかりであると書かれている。これを見れば斉家文化で 象嵌技術が完成していたことがはっきりわかる。 上の展示の一番左の玉器で、この形を琮(そう)と言い、琮は長江下流の良渚文化から黄河上流の斉家文化に伝わったのである。紋様はは牛か羊の獣面紋だと考えられ、二里頭文化の獣面紋の祖型となる紋様である。 左から二番目の仮面のような面具とされる玉器も斉家文化のものである。象眼するものには赤い石や白いものあるのだが、目の部分と歯の部分に白い貝が嵌め込まれているように見える。もしこれが海産の貝であったりすれば、中国の海岸部と内陸部との交易があった証拠になる。(桜貝などは中国の南海から奥地に運ばれていた例がある)  左から三番目の黒い玉の土台に象嵌のある玉人像  左から四番目は夏王朝の銅牌飾とソックリな青銅器である。盾形の外形、人の顔、トルコ石の象眼、4つの穴のある耳など、夏王朝の銅牌飾とソックリ。  一番右のものは玉璧(ぎょくへき)と言われるもので、象嵌のある玉璧が斉家文化のものとしてアモイの上古文化芸術館に展示されている。象嵌のない玉璧は斉家文化で、かなり出土している。  上のものの他にも古文化芸術館には、斉家文化の象嵌された玉器が展示されている。
私の収集品の象嵌のある玉器と、アモイの上古文化芸術館の展示品とを比較して見ると多くの共通点がある。このことから私の収集品は斉家文化のものだと言える。また上古文化芸術館の展示品を見れば、斉家文化には象嵌のある玉器はあると証明できるのである。 以上 |