印幡沼および周辺水域の魚類2000.1改訂
印旛沼および周辺の水域で見られる魚類を集めてあります。魚名をクリックして図版と説明文をみてください。
ヌマチチブ ギンブナ モツゴ クルメサヨリ コイ タイリクバラタナゴ
タモロコ ヤリタナゴ ブルーギル ブラックバス メダカ シマドジョウ
ワタカ (1999.11追加)
ホトケドジョウ Lefua costata
costata(KESSLER)ドジョウ科
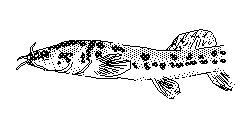 全体的にずんぐりして、胴体の断面は丸い。ちょうど、ドジョウとハゼの中間のような体形をしている。
全体的にずんぐりして、胴体の断面は丸い。ちょうど、ドジョウとハゼの中間のような体形をしている。
千葉ではダルマドジョウとも呼ばれる。小川や小溝など水が澄んだところや湧水の周辺に生息する。雄は4〜5cm、雌は5〜6cmに成長する。産卵は3〜6月に水草や枯れ草に行う。一部(青森県、中国地方西部)を除く本州、四国東部に分布。アジア大陸にもいる。
■もう、何年も前になりますが、佐倉市南部の護岸工事された用水路で見つけたことがあります。底の割れ目から湧いている水によって周囲の小さな砂がつもっていて、その中で暮らしていました。「いるのだ」という安心感と「なにかきびしいところでいきているな」という哀れみを感じました。
ウナギAnguilla japonica TEMMINCK et SCHLEGELウナギ科
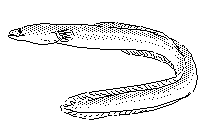
腹鰭はない。胸鰭はある。背鰭、尾鰭、尻鰭がつながっている。岩場や石垣にいる。夜行性で小魚、エビ、貝、昆虫などを食べる。冬は活動しない。5〜12年間、淡水域で生活後、8〜10月に降海する。台湾、ルソン島東方で産卵すると考えられている。幼体はレプトセファルスとよばれる。体長5〜6cmのシラスウナギに変態すると秋から春にかけ川を遡上する。日本全国に分布。朝鮮半島、中国大陸、ベトナムにも分布。
カダヤシGambusia affinis(BAIRD et GIRARD)カダヤシ科
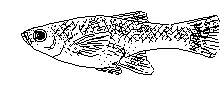 熱帯魚のグッピーに非常に似ている体形。
熱帯魚のグッピーに非常に似ている体形。
浅い止水域に生息し、イトミミズや浮遊生物を餌としている。汚濁や高塩分にも強い。原産地は北米のテキサス周辺。ボウフラをよく食べるので日本にも1913年より度々、移入された。雄は2-3cm。尻鰭の第3-5軟条が棒状に伸び交尾器となっている。日長12.5時間以上、水温20度以上で交尾,1回で30尾前後を産む。
別名タップミノー。
カムルチーChanna (Ophicephalus) argus CANTOR タイワンドジョウ科
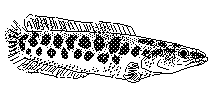
水の濁った底の部分や水草の繁った場所に多い。水中の酸素が不足すると空気を呼吸する。魚やカエルを食べる。5〜8月に浅い場所の水草に雌雄が協力し直径1mほどの浮き巣をつくり産卵する。1年で体長25cm、4年で50cmほどに成長する。原産地はアムール水系〜長江。俗にライギョとよばれている。全国に分布。
ヨシノボリ ハゼ科−ハゼ亜科
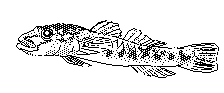
河川によく見られるハゼの仲間である。しかし、型が様々である。かってはヨシノボリという魚にいろいろな型があると言われていたが、現在はそれぞれが種となっている。シマヨシノボリ、オオヨシノボリ、ルリヨシノボリなど多くの種がある。印旛沼周辺で見られるものは眼から口にかけての縞模様が割合とはっきりしており、ルリ色の斑が体表に見られるものが多い。種によって海と川を回遊するものや川のみ一生をすごすものなどがいる。全国、朝鮮半島、中国大陸に分布する。
ヌマチチブTridentiger kuroiwae brevispinis(KATSUYAMA, ARAI NAKAMURA) ハゼ科−ハゼ亜科

頭部の淡黄色の斑紋がある。また、第1背鰭鰭条が著しく伸びる。水生昆虫、そう類を食べる。産卵は3〜8月、石垣、木片、空カンに行う。ふ化した稚魚は降海する。8〜10cmで遡上する。一生を池や沼で過ごすものもある。チチブとは別種。チチブと共存する場合はヌマチチブの方が上流にいる場合が多い。
ギンブナCarassius gibelio langsdorfi(VALENCIENNES)コイ科−コイ亜科
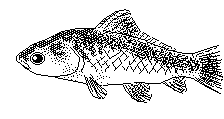
マブナとも呼ばれるが、これは地方名。雄の数が極めて少ない。関東地方では3倍体の雌がほとんどで雄は皆無。3-7月に水面に浮かんだ水草などに産みつけらる。卵はウグイ、ドジョウなどの精子を刺激剤として人工処女生殖させることができる。背鰭軟条数14-17本。雑食性。沖縄を含む全国に分布。
モツゴPseudorasbora parva(TEMMINCK et SCHLEGEL)コイ科−ヒガイ亜科

俗にクチボソと呼ばれる。雑食性。4〜8月に石や貝殻、ヨシなどの茎に産卵する。8〜10cmほどまで成長する。用水路や小川にもよくいる。流れの緩やかな泥底部を好む。口が体に比べ小さく、上向きなのが特徴。生殖期に雄の口のまわりに追星と呼ばれる小さな粒状のものがあらわれる。北海道を除く全国に広く分布している。北海道にも分布を広げているようである。
クルメサヨリHyporhamphus (Hyporhamphus) intermedius(CANTOR)サヨリ科
![]()
近縁種にサヨリがいる。サヨリは下顎先端が赤くなるが本種はならない。大きさもサヨリの半分ほど20cmくらいである。夏に淡水域に遡上する。産卵期は4−8月。藻、水草に産む。本州、四国、九州に分布。
■ある年の夏に印幡沼でつりをしていると水面できらきら光るものがありました。よく見ると笹の葉のような魚でした。何回もトライしやっとつりあげました。それがクルメサヨリでした。弱い魚ですぐに死んでしまいす。
コイCyprinus carpio LINNNAEUSコイ科−コイ亜科
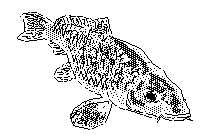
2対の口髭を持つ。野性のノゴイと養食用のヤマトゴイを総称しマゴイという。水草の破片、そう類、砂泥中の底生動物などを食べる。貝類を好んで食べる。産卵は18〜26度の範囲で行われる。卵は水草に付着する。淵など流れの弱い部分にいる。咽頭歯という臼歯状のしくみをもち硬い貝類なども好んで食べる。分布は全国。
タイリクバラタナゴRhodeus ocellatus ocellatus(KNER)コイ科−タナゴ亜科
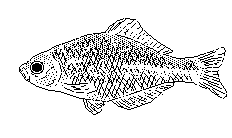
半底生及び付着性生物を食べる。産卵期には雄の体表は緑色や赤色で彩られる。原産地は朝鮮半島南部、中国大陸南部。最近は多くの河川、池などで在来のニッポンバラタナゴを駆逐している。6〜8cmほどに成長する。産卵は3〜10月。雄が貝を中心になわばりをつくる。卵は貝に産みつけられる。亜種になるニッポンバラタナゴRhodeus ocellatus smithi(REGAN)は琵琶湖淀川以西本州、九州に分布している。タイリクバラタナゴに比べ、婚姻色は地味。また、腹鰭前縁に白帯がない。産卵期は5−6月。
。
タモロコGnathopogon elongates elongates (TEMMINCK et SCHLEGEL)
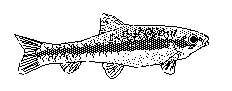
水生昆虫、浮遊動物、小魚、水草等を食べる。2年で9〜10cmほどまで成長する。流れの緩やかな場所を好み数も多い。4−7月に砂底部、水草などに産み付ける。本州西部、四国、九州に分布していたが、関東、東北にも分布は広がっている。口のそばに短いひげが一対ある。
ヤリタナゴTanakia lanceolata(TEMMINCK et SCHLEGEL)コイ科−タナゴ亜科
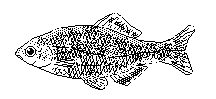
日本のタナゴ類の中では分布域が最も広い。タナゴとしては体高が低い。比較的、長い口髭を持つ。体長は6〜8cmぐらい。背鰭に縞模様がある。側線は完全。産卵期雄は背が金属光沢の青緑色となる。水草につく動植物を食べる。4−8月にマツカサガイなどに産卵する。本州、四国、九州の一部に分布。
ブルーギルLepomis macrochirus RAFINWSQUEバス科

体側に7〜10本の暗色横帯がある。原産地は北アメリカ東南部。日本には1960年、移入され各地の河川、湖沼に広まった。雑食性が強い。25cmほどに成長する。産卵期は5−7月。
ブラックバスMicropterus salmoides salmoides (LACEPEDE)バス科
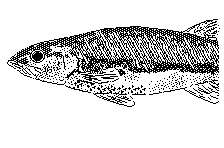
別名ブラックバス。体側に暗黒色の縦縞がある。魚、エビ、カエルなどを食べる。体長は40cmほどに成長する。原産地は北アメリカ東南部。日本へは1925年、芦ノ湖に移入され、各地に広まった。産卵期は5−7月。
メダカOryzias latipes(TEMMINCK et SCHLEGEL)メダカ科
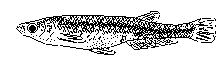
浅い池、沼、水田に多い。温度変化、塩分、汚濁に強い。水面に群れている。浮遊生物を食べる。春から秋の朝方に長い糸のついた卵を水草に生み着ける。体長は2cmほど。日照時間が十分と水温が十分になると産卵する。卵は水草に付着する。分布は沖縄を含む全国。北海道は局地的なようである。色素のちがいによりヒメダカ、シロメダカ、アオメダカなどがある。
シマドジョウCobitis biwae JORDAN et SNYDERドジョウ科
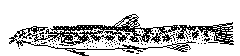
緩やかな流れの場所に生息する。砂の中の小動物やそう類を食べる。口から食物を吸い込みさい孔から砂粒などを吐き出す。15cmほどに成長する。4〜6月に小川や小溝に遡上し水生植物の根や茎に産卵する。雄の胸鰭の先は鋭くとがる。日本特産種で本州、四国に分布。染色体数の2倍体、4倍体などのものがそれぞれの地域に分布している。関東のものは2倍体で小さく10cm以下のものが多い。
ドジョウMisgurnus anguillicaudatus(CANTOR)ドジョウ科
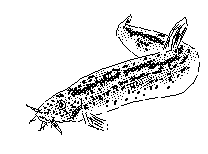
通常の河川より水田や用水路に多い。口髭は5対で下顎の2対はごく短い。酸素が欠乏すると水面に上がり、口から酸素を吸い腸呼吸を行う。雄が雌に巻きつき産卵を促す。10〜12cmになるが雌の方が雄より大きい。産卵は4−7月、水田などで行う。全国に分布。
ソウギョCtenopharhyngodon idellus(VALENCIENNES)コイ科クルター亜科
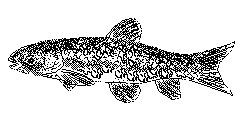

草食性の大型魚類。原産地はアジア大陸東部で日本には明治時代に移植された。主にアシやマコモの葉や茎を食べ、1m以上になるものもある。中国では食用にされる。日本では利根川水系のみで繁殖する。この魚の卵は産み落とされると水に流される性質がある。およそ50時間後に孵化する。このため十分に長さのある川でないと海に出てしまい卵は孵化できなくなってしまう。その長さという条件を満たしている利根川のみで繁殖できる。産卵期は6−7月。
ワタカIschikauia steenackeri(SAUVAGE)コイ科クルター亜科
 (写真提供:塩島正紀氏)
(写真提供:塩島正紀氏)
もともとは琵琶湖、淀川水系の魚。関東地方には移入された。草食性が強く日本在来としては唯一の草食魚。頭部の後ろの背が盛り上がる。側線は下方に湾曲している。腹鰭から肛門にかけ、竜骨状の突出部がある。1年で10cm弱。最高で30cmくらいになる。