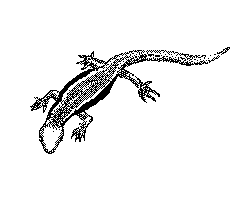みたい生物をクリックしてください。
ヒキガエル ニホンアカガエル トウキョウダルマガエル アマガエル シュレーゲルアオガエル
アカミミガメ
1930年代、北アメリカより移入。稲を食害すると嫌われたが、田の雑草であるヒルムシロやヒルを食べるため重宝がられる一面もある。
■「アメリカザリガニの帰化により日本在来のザリガニは駆逐された。」と言われますが最近ではそうではないと言われています。もともと、日本にいたザリガニは非常に棲息条件に対してデリケートな種でアメリカザリガニとは棲息域が重複しなかったとのことです。
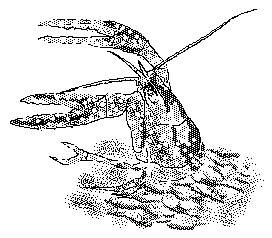
ザリガニについてもっとくわしく知りたいときはここへ行ってみよう
体長10〜15cmほどのエビで雄の第2胸脚部が長く体長の1.5倍に達する。雌は雄の半分ほどの長さ。
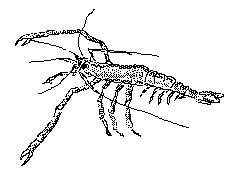
沼池にすむ体長3cmほどの小型のエビ。似たものとしてヌマエビがあるが、頭胸部の形状で区別する。
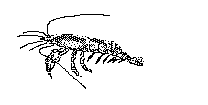
腹が鮮やかな赤色をしていることから、アカハラともよばれる両生類。体長は90〜130mmほどで雌の方が大きい。卵は折り畳んだ水草に1個ずつ産みつけられる。
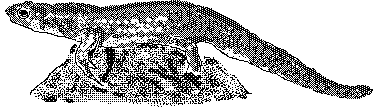

体長10〜20cmほどの大型のカエル。緑褐色に不規則な暗褐色の斑紋がある。北アメリカ原産。食用とされるため食用ガエルともよばれる。鳴き声が牛に似ている。
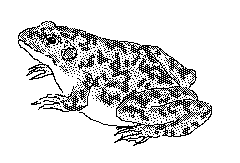
ガマガエル、イボガエルなどとよばれる大型のカエル。産卵期になると雄の皮膚はなめらかになり、赤黄色を帯びる。卵塊は太いひも状で長さ8m、8000個にもおよぶ。
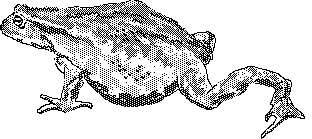
水田近くなどにいるが、陸生のカエル。
トノサマカエルによく似るが関東はダルマガエル。体長は6〜10cmほど。
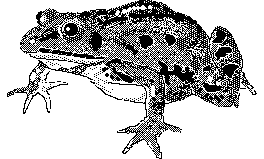
ごく普通にみられる小型のカエル。通常、緑色をしているが体色は変化する。鼻孔から眼、体側にかけ黒い縞がある。指先は平たく物に吸い付きやすい構造をしている。
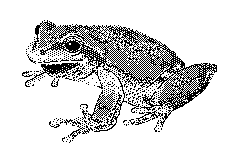
4月ごろ田などにある泡状の白い卵塊はこのカエルのもの。アマガエルに似るが、体側の縞がなく、アマガエルに比べやや頭部が大きく感じる。
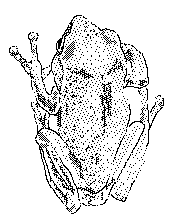
甲長25cmほどに成長する。首に黄色の線が見られる。危険が迫ると悪臭を放つ。
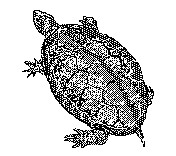
甲長18cmほどに成長する日本特産の種。子はゼニガメとも呼ばれる。甲の後部がぎざぎざになっていることでクサガメと区別できる。帰化したアカミミガメ(ミドリガメ)におされ数は減少している。
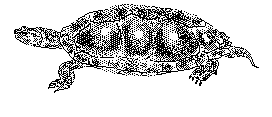
アカミミガメ
ミドリガメといったほうが通りがよいかもしれない。縁日や祭り、ペットショップでよく売られている緑色のカメ。緑が鮮やかなのは小さいときだけで、大きくなると緑色はわかりにくくなり、ほとんど茶褐色になる。クサガメなみの大きさまで成長する。側頭部の赤いラインからアカミミガメ(レッドイヤータートル)の名がある。これも帰化種であるが自然の河川で著しく増加している。このほかに最近ではカミツキガメ、ワニガメなど帰化種の猛威が話題となる。

小型のハチュウ類独特の形状をしたあしで窓ガラスなどに張り付く。平たい体をしており、気の皮の下や家具のすき間などに潜み物の移動にまぎれ移動する。卵も頑丈な殻をもつ。
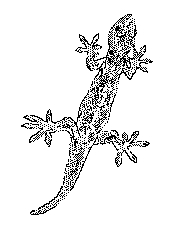
数的には多い毒ヘビ。毒は非常に強い。頭が三角形なのが特徴。
体側の斑紋状の模様が目立つ。
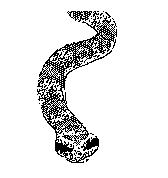
淡水貝ではわが国で最大の大きさになり、殻長25cmほどに成長する。外は黒色で地味だが内側は真珠のような光沢をもつ。以前は貝柱が食用に、貝殻がボタン、細工物に使われた。

殻高30mm、殻径12mmほど。水のきれいな砂底にすむ。ごくふつうにみられる。肺臓ジストマや吸虫の中間宿主。ホタルの幼虫のえさとなる。
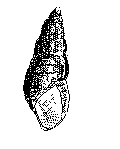
戻るv
トカゲより多い。ごく普通にみられる。5月から8月に2,3回。1回に2〜7個の卵を産む。
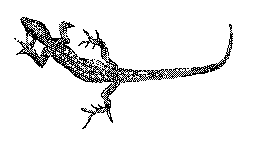
正式にはニホントカゲという。変温動物で冬は冬眠して過ごす。春には雄ののどあたりに赤味をおびた婚姻色がでる。成長にともない体色を著しく変化させる。子のほうが体側のストライプ模様がはっきりとしている。6月頃に産卵し産卵数は6〜10個。